
BLOG
ブログ
頭のてっぺんが熱い|頭頂部が熱い原因は頭部内うつ熱
- カテゴリ:
- 頭や顔の悩み
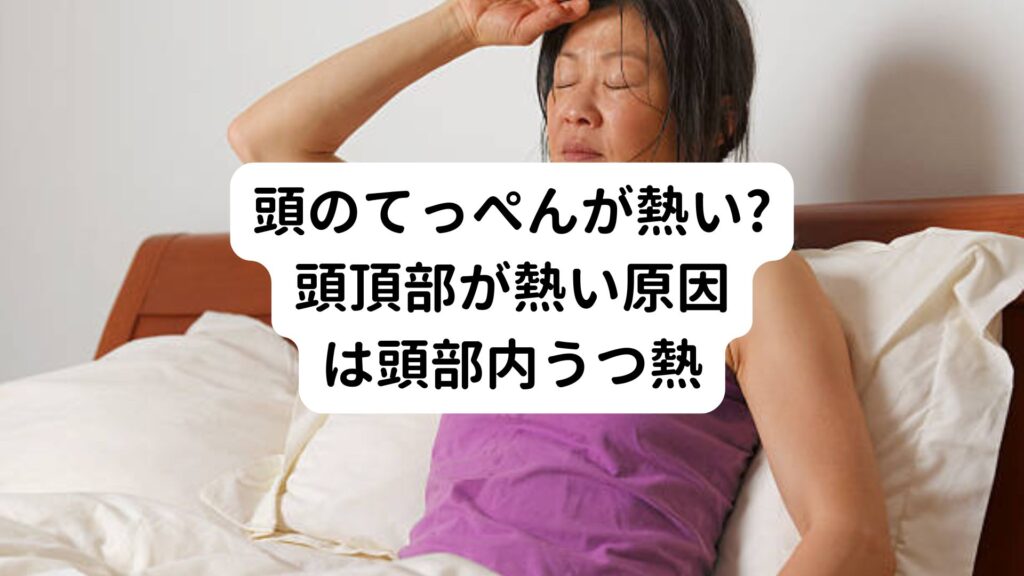
公開日:2024年02月25日
更新日:2025年09月23日
このブログを監修している鈴木貴之は国家資格であるはり師免許、きゅう師免許、柔道整復師免許、心理カウンセラーを取得した資格保有者です。
目次
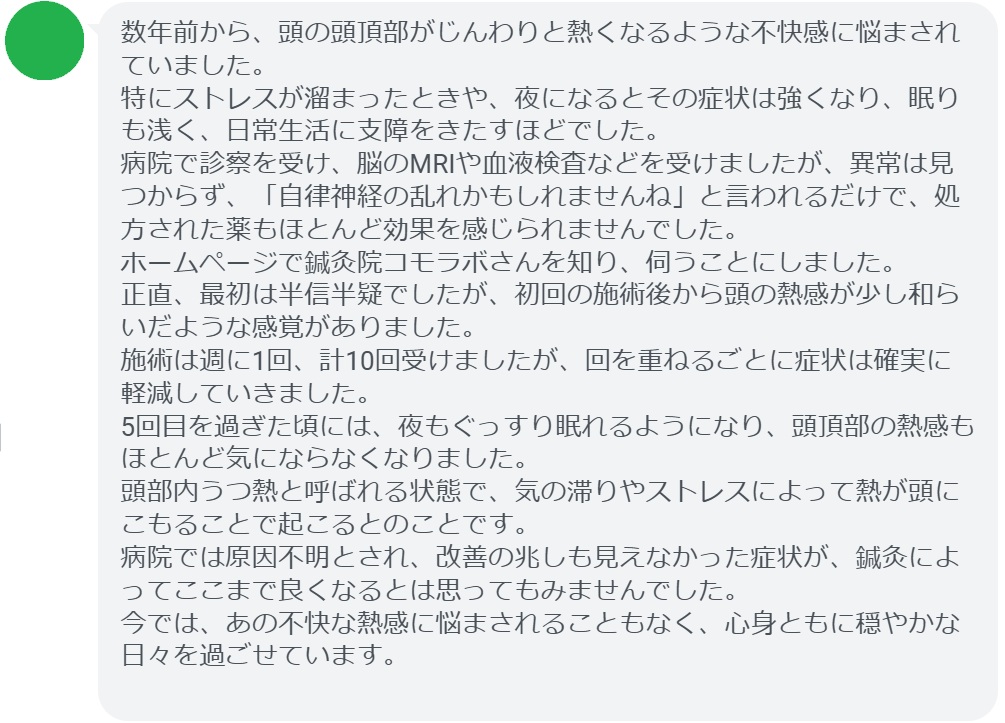
頭のてっぺんが熱い症状は頭部内うつ熱という状態
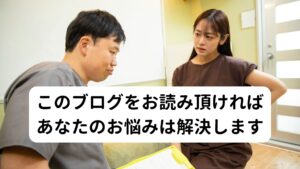
「ストレスが溜まると頭のてっぺんが熱くなる」
「モニター作業をすると頭皮がカッカと熱くなる」
「一度頭が熱くなると全然熱が冷めない」
このような状態が治らず悩まれている方はおられないでしょうか。
これは一つに自律神経の乱れ(自律神経失調症)が関係しています。
自律神経失調症は病院などで「原因がわからない症状」に付けられる診断であることがよくあります。
そのため検査をして異常が見つからないと医師から「自律神経の問題ですね。」と一言で診察が終わってしまうことも多々あります。
「どうやって改善したらよいのか」のでしょう。
明確な道のりを示してくれる医療機関は案外少ないように思います。
結局は薬は処方されるけれど、なかなか改善されない。
当院でもそのような流れから治療を受けにくる方がとても多いです。
鍼灸治療の領域ではこのような頭部の熱感症状を「頭部内うつ熱(とうぶないうつねつ)」と呼びます。
今回は「頭のてっぺんが熱い|頭頂部が熱い原因は頭部内うつ熱」と題して頭部に熱感が起こるメカニズムと鍼灸治療の有効性について解説します。
頭皮が熱い原因は脳のオーバーヒートが影響している
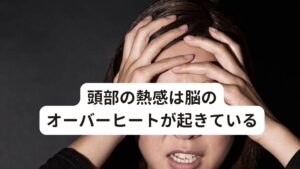
頭部内うつ熱は身体にこもった熱(うつ熱)が特に頭部内に上昇して「頭に熱っぽさを感じる状態」のことをいいます。
頭部に熱く感じますが、発熱したときのような体温が上昇している状態ではありません。
そのため体温を測っても上がっていませんし、おでこを触っても熱感を感じることもありません。
この原因にはスマホ、パソコンなどを利用した頭脳に偏った作業で頭を使い過ぎた疲労が影響しています。
頭の使い過ぎ→頭が疲労を起こし熱が溜まる→熱が冷めずに脳がオーバーヒートする→自律神経が乱れる
主にこのような流れで頭部内うつ熱は起こります。
しかし、こういった症状が起こっているとしても病院では検査では異常が見当たらず「原因不明」と診断され続けてしまい、
結果として頭痛や不眠などの自律神経症状を引き起こし現代社会の問題となっているのが現状です。
頭部内うつ熱が起こるメカニズム
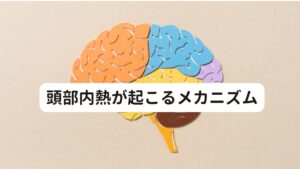
脳は体の状況を五感(視覚・聴覚・平衡覚・味覚・嗅覚)で感知し、その感知した情報を元に自律神経やホルモンを介して調節しています。
この入ってくる情報と、出力の仕組みがうまく循環していると、心身は正常に機能した状態です。
しかし現代社会の生活では、入ってくる入力情報(スマホやパソコンなど)が過剰になると、入力と出力のバランスが崩れてしまうことがあります。
高齢者の場合は、この機能のアンバランスが起きていると外気の温度を感知する能力の低下となり熱中症になりやすい一因と考えられています。
このように脳の入力と出力のバランスが崩れると、脳は疲弊し「頭部内うつ熱」が生じます。
脳は身体的不調(頭痛やめまいなど)だけでなく、思考や感情という目に見えない情緒や心理面にも影響を与えるため、うつ症状や気分の落ち込みなども引き起こします。
内臓や器官の機能異常による身体的な失調、脳の機能異常による情緒や思考の失調などは「頭部内うつ熱」と因果関係があることが最近わかってきています。
頭部内うつ熱の主な症状は頭痛や発熱
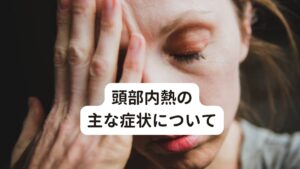
頭部内うつ熱の主な症状は以下の通りです。
・動悸
・めまい
・立ちくらみ
・頭痛
・発熱
・うつ
・胃腸障害
・メニエール
・不眠症・パニック障害
・耳鳴り
・不安症
・慢性疲労症候群
・多汗症
・アレルギー症状
・イライラ
・眼精疲労
・ドライアイ
・更年期症状
・のぼせ
・健忘症
頭部内うつ熱が起こるとこのような自律神経失調症と考えられている心身の症状が様々に起こります。
その中でも多くのケースで「頭のてっぺんが熱い」という症状が起こります。
人間の体温が低いのは脳を熱から守るため
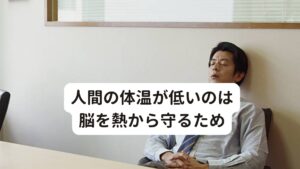
人間の体温はなぜ36.5℃に保持されているのでしょうか。
その理由に脳を守るためがあります。
人間以外の動物の犬、猫、猿などの体温は37~40℃と高い体温です。
この人間と動物の体温の違いは脳の違いともいってよいでしょう。
人間は他の動物に比べて脳を異常なほど発達させ、言語や高度な文明を生み出してきました。
人にとって脳はいわばコンピューターで情報処理をする所です。
そのためコンピューターである脳は使用すればそれだけ熱を持ちやすく放熱できなければオーバーヒートしてしまいます。
体温が36.5℃を保持しているのはこういった理由で他の動物に比べると低めの温度設定しているのです。
活動で生じる身体の熱を放熱できない影響が原因
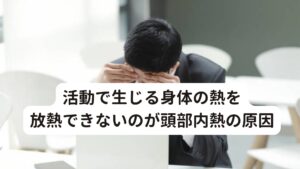
発熱、うつ熱、頭部内うつ熱など体内で起こる熱にはいろいろありますが、この熱の多くは細菌やウイルスに感染したときに起こります。
これは身体が免疫力を働きやすくするために「発熱」という状態を自ら作っています(免疫細胞は37.5℃で最も働くとされています)。
たとえ発熱しても体の機能が正常に働いていれば、適切な段階で熱は平熱に下がっていきます。
これに対してうつ熱や頭部内うつ熱は、体の体温調節や血流がおかしくなっ て適切な体温を維持する働きができなくなった状態をいいます。
例えば、風邪で発熱をしても汗をだして体温調節ができればうつ熱状態は起こりません。
しかし、体温調節がうまくいかないだけで、筋肉や脳の活動で生じた熱が発散できなかった熱がこもってしまいます。
このうつ熱が頭に集中してこもった状態を頭部内うつ熱と呼んでいます。
現代人の生活は頭に熱がこもりやすく、その影響で自律神経や心身の不調を引き起こしているのです。
※ちなみに体内の酵素が働く温度は36~42℃であり。36℃以下では酵素が充分に働かなくなります。
【最新情報】医療機関では教えてくれない効果的な対処法

【最新情報】
このような頭部が熱くなる頭部内うつ熱でお悩みの方によく質問されるのが「頭は冷やしてもいいか」ということです。
結論からいいますと「冷やしてもよい」と当院では考えております。
しかし、「頭寒足熱」と昔から言われているとおり積極的なセルフケアとして推奨するのは「足を温めること」です。
東洋医学では頭が熱くなる原因は足部に留まるべき熱が上昇して頭部に溜まってしまった結果と考えます。
そのためその熱を足部に戻すためには足部を温めることが必要です。
この考えては医療機関では教えてくれません。
しかし、頭を冷やすと同時に足部をしっかりと温めることが頭部内うつ熱の解消につながる一番よい対処法です。
病院で治らない頭皮が熱い症状を改善するには鍼灸治療
このような頭が熱くなる頭部内うつ熱を完治させるには東洋医学に基づく鍼灸治療が効果的です。
東洋医学ではこのような脳の機能の低下を改善するには「自律神経の正常化と血流改善」と考えられています。
そのため当院ではこの改善を目的とした一人ひとりの体質に合った効果的なポイントに鍼灸治療を行います。
当院の鍼灸治療は病院の薬物療法やマニュアル通りの治療ではできない柔軟な鍼灸治療で効果を引き出します。
ぜひ、頭の熱がこもった不調でお悩みの方はご相談ください。
頭頂部が熱い頭部内うつ熱【44歳女性 自営業(東京都在住)】
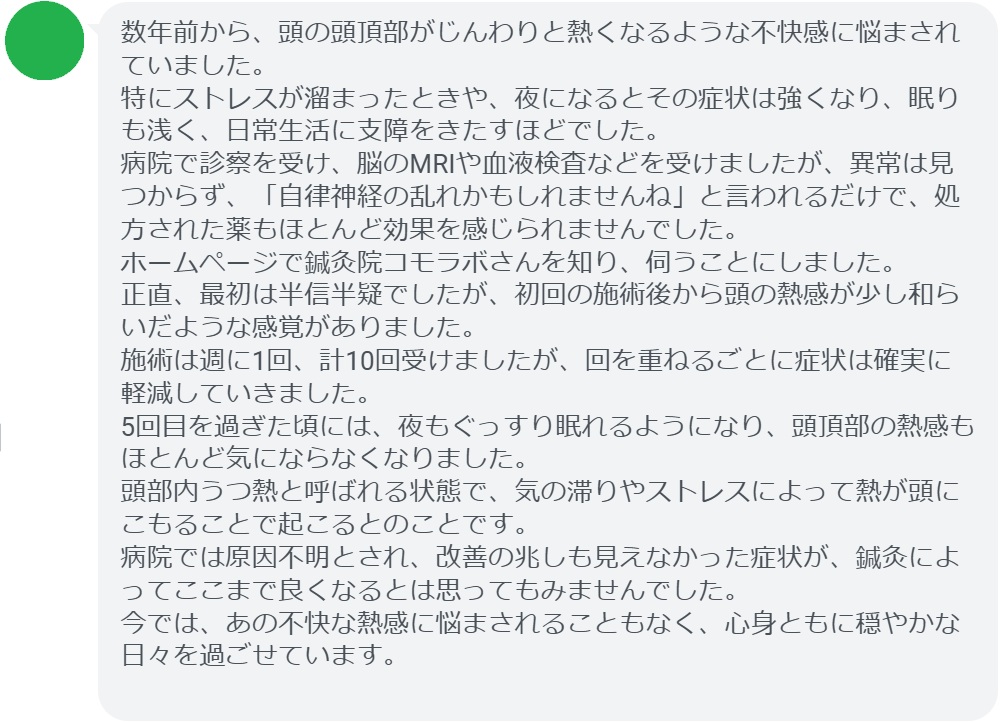
【頭頂部が熱い頭部内うつ熱が改善された方の感想(口コミレビュー)】
・東京都在住/44歳女性
数年前から、頭の頭頂部がじんわりと熱くなるような不快感に悩まされていました。
特にストレスが溜まったときや、夜になるとその症状は強くなり、眠りも浅く、日常生活に支障をきたすほどでした。
病院で診察を受け、脳のMRIや血液検査などを受けましたが、異常は見つからず、「自律神経の乱れかもしれませんね」と言われるだけで、処方された薬もほとんど効果を感じられませんでした。
ホームページで鍼灸院コモラボさんを知り、伺うことにしました。
正直、最初は半信半疑でしたが、初回の施術後から頭の熱感が少し和らいだような感覚がありました。
施術は週に1回、計10回受けましたが、回を重ねるごとに症状は確実に軽減していきました。
5回目を過ぎた頃には、夜もぐっすり眠れるようになり、頭頂部の熱感もほとんど気にならなくなりました。
頭部内うつ熱と呼ばれる状態で、気の滞りやストレスによって熱が頭にこもることで起こるとのことです。
病院では原因不明とされ、改善の兆しも見えなかった症状が、鍼灸によってここまで良くなるとは思ってもみませんでした。
今では、あの不快な熱感に悩まされることもなく、心身ともに穏やかな日々を過ごせています。
実際に当院に受診し改善された患者様の声と改善までの経過を報告します。
下記のリンクから別ページでご覧ください。


鍼灸院コモラボ院長
ブログ管理・編集者
鈴木貴之(すずきたかゆき)
【国家資格・所属】
鍼灸あんまマッサージ指圧師、柔道整復師、心理カウンセラー、メンタルトレーナー 治療家歴14年、日本東方医学会会員、脈診臨床研究会会員
神奈川県の鍼灸整骨院にて15年勤務(院長職を務める)
【施術経過の同意について】
本ブログに掲載する施術の経過の情報は「私は本施術の経過を匿名化して貴院のウェブサイトに掲載することに同意します。」と患者様から同意書を得ております。また氏名・連絡先は公開されません。
【医療受診の案内と施術の注意点】
次の症状がある場合は速やかに医療機関を受診してください。強い胸痛、意識障害、急激な症状の悪化、高熱、持続する出血。鍼灸・整体は有益ですが、抗凝固薬服用中、出血傾向、妊娠初期、感染症の疑いがある方は施術前に必ず医師へ相談してください。
現在、JR三鷹駅北口に自律神経専門の鍼灸院コモラボにて様々な不調の患者様に鍼灸治療を行っている。
【SNS】
Youtube , Instagram , X(Twitter)







この症状に対する質問
毎日頭を冷やしてカロナールとデパスとエペリゾンを一日一回飲んでいますが大丈夫でしょうか?
匿名 様
コメントありがとうございます。
「毎日頭を冷やしてカロナールとデパスとエペリゾンを一日一回飲んでいますが大丈夫か」とのご質問ですね。
当院では西洋薬に関しては基本的に「効果を実感しない薬は飲み続けない」という考えです。
カロナール、デパス、エペリゾンに関して「服用しても効果が実感しない」のであれば中止すべきです。
またデパスに関しては脳、中枢神経に強い作用を与える薬物ですので、たとえ効果が実感していても減薬、断薬を計画するようにしてください。
宜しくお願い致します。