
BLOG
ブログ
ため息が癖の人の心理とは|ため息をつかない方法
- カテゴリ:
- 全身のお悩み
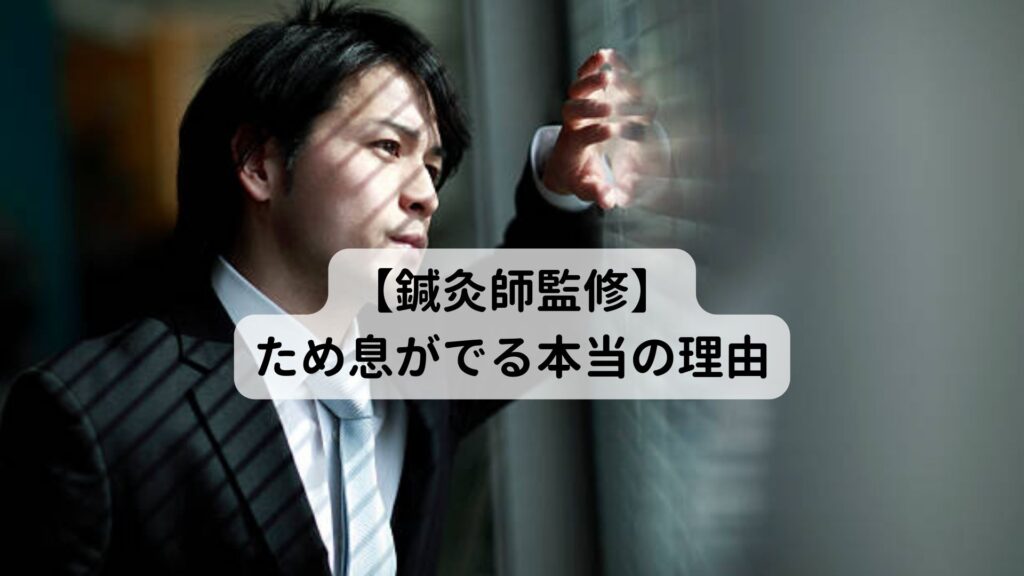
公開日:2023年09月22日
更新日:2024年12月16日
このブログを監修している鈴木貴之は国家資格であるはり師免許、きゅう師免許、柔道整復師免許、心理カウンセラーを取得した資格保有者です。
目次

最近ため息が多いと感じている
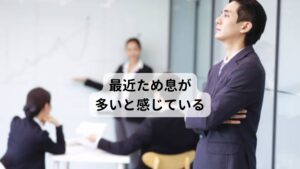
「最近ため息が多く出ている」「何かとため息をしてしまう」「気持ちが落ち着かずため息をしてしまう」など昔に比べるとため息の数が増えていると感じている方は多いのではないでしょうか。
ため息は自分ひとりのときは気にならないですが、職場など人と関わりがある中でしてしまうと悪い印象を与えてしまう可能性もあります。
そのため、なるべくならため息はつかないように癖を治したいと思っている方もおられると思います。
今回は「ため息が癖の人の心理とは|ため息をつかない方法」と題してため息が出る理由を東洋医学の観点から解説します。※1
ため息をすると幸せが逃げるって本当?
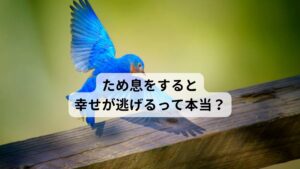
よく「ため息をすると幸せが逃げる」と言われていますがそんなことはありません。
ため息は身体の変調のサインといわれています。
とくにため息は自律神経(交感神経と副交感神経)のバランスの変調を正常に戻そうとして起こる生理現象として考えられています。
そのためため息はする人にとっては健康を取り戻すための呼吸法といえます。
無理に我慢せずにゆっくりと大きくため息をすることで自律神経が整い気持ちもリフレッシュして幸福感が高まるでしょう。※2
ため息は東洋医学では太息と呼ぶ
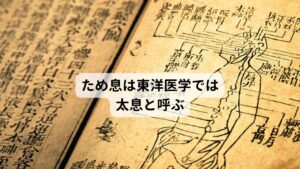
このため息は東洋医学では「太息(たいそく)」と呼び、「情志の失調により肝の疏泄が低下を表す」と説明します。
現代医学で説明するとこれは「精神的なストレスによって自律神経が乱れている」という意味になります。
もう少しわかりやすく説明するならば「精神的なストレスで自律神経の巡りが滞ってストレスが溜まっている」というものです。
東洋医学でも太息は生理現象として捉えており、身体の変調のサインとして考えます。
ため息が多いと感じたらストレスを完治するのが大事

ため息は西洋医学、東洋医学どちらも自律神経に関わるアンバランスを取り戻すための呼吸法であると解説しました。
そのためため息は我慢せずにゆっくりと大きく行いリラックス効果を引き出すつもりで行うことが大切です。
またため息はストレスなど体に不調を起こす負荷がかかっている状態を表します。
そのためその負荷であるストレスや鬱々とした感情を完治するように心がけましょう。
実はカウンセリングによる心理的ストレスの軽減で改善できる
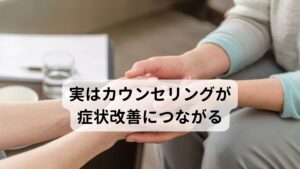
自律神経失調症は「自律神経失調症そのものがストレスに感じる」「治らないことが余計に不安になり症状が強くなる」「ついつい自律神経失調症のことを気にしてしまう」といった不調に対する捉え方や考え方によっても症状を悪化させることがあります。
そのため改善のためには不調そのものに対する捉え方や考え方を修正することがとても重要になります。
日々、知らず知らずのうちに症状を強めてしまったり改善を妨げている心の癖や考え方の癖を、正しく修正し心理的ストレスを軽減させることで自律神経失調症が完治されることが多々あります。
当院でもカウンセリングと鍼灸を組み合わせた方法で治療を行っております。
ぜひ、強い精神的なストレスと不調でお悩みの方はご相談ください。

[参考]
※1 「ため息」について考えてみました。 / 絹谷産婦人科
https://www.kinutani.org/blog/?p=266
※2 Vol.86 ため息をついても幸せは逃げていかない! / 新庄徳洲会病院 院長 笹壁弘嗣
https://www.shin-toku.com/blog/director/index.php?id=86

鍼灸院コモラボ院長
ブログ管理・編集者
鈴木貴之(すずきたかゆき)
【国家資格・所属】
鍼灸あんまマッサージ指圧師、柔道整復師、心理カウンセラー、メンタルトレーナー 治療家歴14年、日本東方医学会会員、脈診臨床研究会会員
神奈川県の鍼灸整骨院にて15年勤務(院長職を務める)
【施術経過の同意について】
本ブログに掲載する施術の経過の情報は「私は本施術の経過を匿名化して貴院のウェブサイトに掲載することに同意します。」と患者様から同意書を得ております。また氏名・連絡先は公開されません。
【医療受診の案内と施術の注意点】
次の症状がある場合は速やかに医療機関を受診してください。強い胸痛、意識障害、急激な症状の悪化、高熱、持続する出血。鍼灸・整体は有益ですが、抗凝固薬服用中、出血傾向、妊娠初期、感染症の疑いがある方は施術前に必ず医師へ相談してください。
現在、JR三鷹駅北口に自律神経専門の鍼灸院コモラボにて様々な不調の患者様に鍼灸治療を行っている。
【SNS】
Youtube , Instagram , X(Twitter)


この症状に対する質問