
BLOG
ブログ
ストレスで噛み合わせに違和感|咬合違和感症候群の治療法
- カテゴリ:
- 頭や顔の悩み
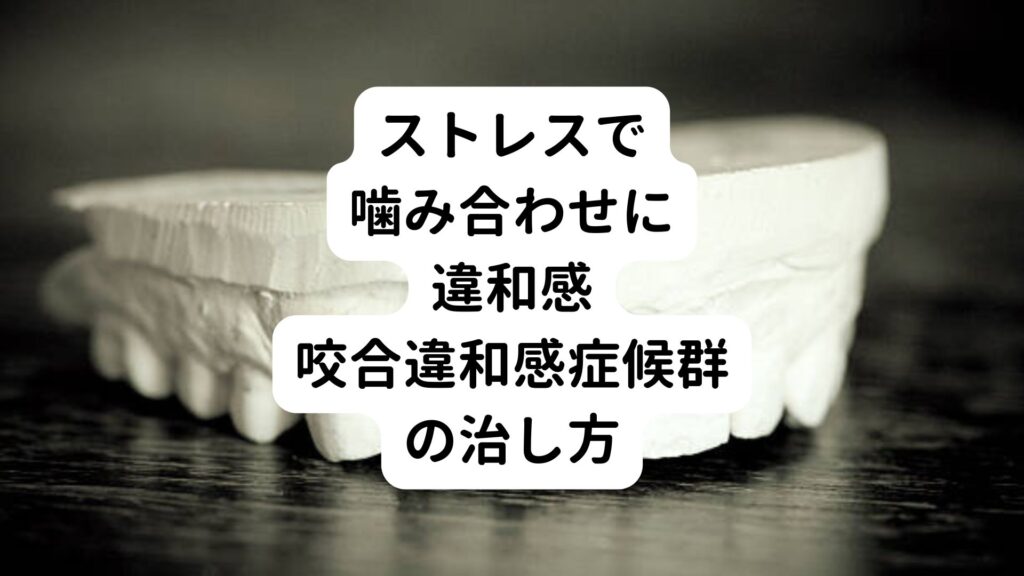
公開日:2024年07月14日
更新日:2024年12月18日
このブログを監修している鈴木貴之は国家資格であるはり師免許、きゅう師免許、柔道整復師免許、心理カウンセラーを取得した資格保有者です。
目次

咬み合わせの異常でお悩みの方に適切なアドバイス
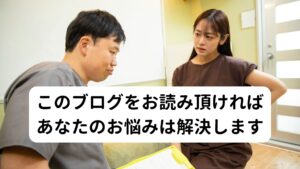
「歯科治療をしてから咬み合わせがおかしくなった」
「歯科では異常がないといわれているが歯の高さがおかしい」
「ストレスで噛み合わせに違和感を感じる」
「食事をするたびに咬み合わせに異常を感じている」
このような不調でお悩みの方はおられないでしょうか。
日々の生活の中で起こるストレスから、心身に様々な不調を感じている方が多くいらっしゃいます。
先にあげた口の中で生じている不調も些細な歯の高さの違いや引っかかりに脳が過敏に反応して起きている心身の不調の可能性があります。
今回は「ストレスで噛み合わせに違和感|咬合違和感症候群の治療法」と題して、咬合違和感症候群の原因と正しい治し方について解説します。
咬み合わせのズレが原因?咬合違和感症候群とは
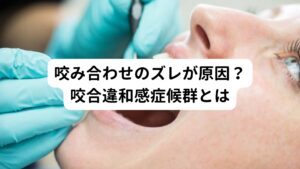
咬合違和感症候群(こうごういわかんしょうこうぐん)とは、歯の神経、歯周病、咬み合わせの筋肉、あごの関節に問題はみられず、さらに様々な検査をおこなっても異常がみられないにも関わらず、主訴として咬み合わせの違和感、不快感が生じている状態をいいます。
歯は髪の毛1本でも噛むと脳が異常を感知する、非常に繊細な器官と言われています。
人によってはわずか0.1㎜の差でも、咬み合わせがずれることで、脳にストレスを感じるということもありえます。
咬合違和感症候群はこういった通常ではストレスと感じない程度の変化に対しても過剰に脳が反応して起きている不快感をさします。
咬合違和感症候群が起こる原因は脳の機能異常
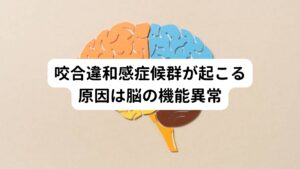
咬合違和感症候群は歯科治療をきっかけとして発症する人が多い傾向にあります。
歯科で咬み合わせの異常を訴えたときに多くの方が「とくに問題ない、気にし過ぎではないか」と歯科医師に指摘された経験があるかと思います。
しかし、咬合違和感症候群は神経質や気にし過ぎではなく、脳のわずかな機能異常が原因とされています。
発症しやすい一つの例では歯科治療後の歯、顎関節、咬み合わせに関与する筋肉や関節などの動きの情報が正確に脳に上手く伝わらず、歯科治療前の咬み合わせのイメージが脳に残っていることで、それが違和感や不快感を生み出して咬合違和感症候群が起こると考えられています。
咬合違和感症候群は精神的な病気が引き起こしている可能性も
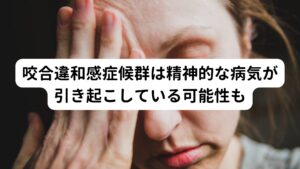
歯科領域では咬み合わせの異常を訴える原因について
・歯並びの乱れ
・ストレス
・歯ぎしり
・噛みしめの癖
などが一般的に考えられます。
しかし、咬合違和感症候群はうつ病や統合失調症などの精神的な病気が、発症の原因に関わっていることがあります。
咬み合わせによる違和感や不快感があると口の中の異常と思いがちですが先ほども解説したとおり「脳の機能異常」として治療することで不調が解消される可能性は高まります。
咬合違和感症候群は中高年の女性に起こりやすい
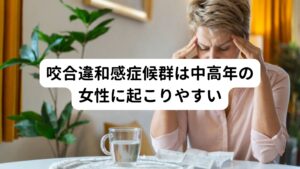
舌痛症と同様に中高年(初診時の平均年齢は50代前半が多い)、女性(女性が7~8割)に多い傾向にあります。
主に症状は
「咬み合わせがおかしい」
「どこで咬んでよいのか分からない」
「咬み合わせが不快で気になる」
といった症状が起こります。
歯科治療後に発症する人が多く、治療後の微細な咬み合わせの変化に対応できずに不調を訴えます。
そのため理想の咬み合わせを求めて、いくつもの医療機関を転々とする人が多い傾向があります。
咬合違和感症候群が起こる最も多いパターンは軽い咬み合わせの違和感から始まり、咬み合わせの調整、つめ物の交換、抜歯をおこなっていくうちに症状が悪化してしまい重症化していくものです。
咬合違和感症候群が発症するきっかけはどのようなものがあるか

咬合違和感症候群が発症するきっかけには以下のようなものがあります
・さし歯やかぶせ物の装着
・入れ歯の作製
・矯正治療
・インプラント治療
・生活環境の変化(転職、離婚、死別など)
歯科治療に関わるものは上位4つのですが、咬合違和感症候群が起こる要因には生活環境の変化も複合的に関連しているため心理的なストレスも含めて考える必要があります。
患者さんが訴える口内の主な症状
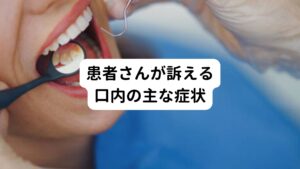
・咬み合わせがおかしい
・どこで咬んでよいのか分からない
・咬み合わせが不快で気になる
・歯科治療後から咬み合わせ悪くなった
・咬むと歯や顎がずれる、すべる感じがする
・歯の当たり具合が悪い
・咬み合わせが高い、当たりすぎている
・咬み合わせが低い
・咬み切れない
など
先ほども解説したとおり、歯科での検査上はとくに異常がないにもかかわらず、脳の機能異常によってこのような不快感や違和感を脳が認知してしまうことで起こります。
患者さんが訴える全身の症状

咬合違和感症候群が慢性的になると心身へのストレスが積み重なって自律神経失調症が起こり様々な全身症状が起こります。
・頭が重く、ぼーっとする
・顔が緊張してゆがむ
・背中の痛み
・肩こり
・めまい
・頭痛
・腰痛
・倦怠感
など
咬合違和感症候群における必要な治療とは
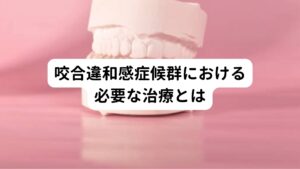
咬合違和感症候群のほとんどは咬み合わせの高い、低い、歯の形や当たり方が原因ではなく、脳のわずかな機能異常が主な原因です。
そのため必要な治療は脳の機能異常を正常な働きへと回復させることです。
しかし、咬合違和感症候群の患者のほとんどが、「咬み合わせを調整しないと絶対に治らない」と考えており、歯科や口腔外科の領域でレントゲン写真の撮影、咬み合わせの検査をおこない咬み合わせの治療をおこないます。
そのため咬み合わせそのものに異常がないにも関わらず咬み合わせの治療を繰り返してしまうと症状が悪化し、かえって治りにくくなることがあります。
歯科では咬み合せの治療はおこなわず、一時的にマウスピースを使用して経過を観察する治療をすることがあります。
矯正治療も抜歯などの外科的な治療も要注意
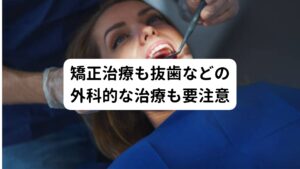
歯科における咬み合わせの治療と同様に、歯並びの治療(矯正治療)や抜歯などの外科治療も症状が悪化し、かえって治りにくくなることがあります。
これらの外科的な治療も慎重におこなう必要があります。
そのほかの治療として、咬み合わせに問題がない場合はTCH(歯列接触癖)の解消で咬み合わせの違和感を改善していくこともあります。
咬合違和感症候群は鍼灸で改善できます
咬合違和感症候群はストレスが積み重なることで起こる脳の機能異常が原因です。
そのため西洋医学ではその脳の機能異常を鎮静させるために抗うつ薬や抗不安薬による薬物療法を行います。
しかしこの薬物療法はあくまで対処療法であるため根本的な改善はできません。
しかし、東洋医学に基づく鍼灸治療は一人ひとりの体質を診断することで咬合違和感症候群の原因を各々の体質から発見し脳の機能異常を治療で改善することができます。
「どこに行けば自分の不調を正しく改善できるかわからない」と治療方法でお悩みの方は当院にお気軽にご相談ください。
当院で患者様の治療実績はこちらから
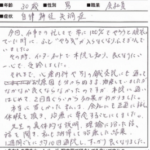
実際に当院ご来院になって改善された患者様の声と改善までの経過を報告します。
同じようにつらい思いをされている方の役に立てるのならばと皆さん快く掲載を許可頂きました。
これを読まれている患者様のご参考になれば嬉しく思います。
下記のリンクから別ページでご覧ください。


鍼灸院コモラボ院長
ブログ管理・編集者
鈴木貴之(すずきたかゆき)
【国家資格・所属】
鍼灸あんまマッサージ指圧師、柔道整復師、心理カウンセラー、メンタルトレーナー 治療家歴14年、日本東方医学会会員、脈診臨床研究会会員
神奈川県の鍼灸整骨院にて15年勤務(院長職を務める)
【施術経過の同意について】
本ブログに掲載する施術の経過の情報は「私は本施術の経過を匿名化して貴院のウェブサイトに掲載することに同意します。」と患者様から同意書を得ております。また氏名・連絡先は公開されません。
【医療受診の案内と施術の注意点】
次の症状がある場合は速やかに医療機関を受診してください。強い胸痛、意識障害、急激な症状の悪化、高熱、持続する出血。鍼灸・整体は有益ですが、抗凝固薬服用中、出血傾向、妊娠初期、感染症の疑いがある方は施術前に必ず医師へ相談してください。
現在、JR三鷹駅北口に自律神経専門の鍼灸院コモラボにて様々な不調の患者様に鍼灸治療を行っている。
【SNS】
Youtube , Instagram , X(Twitter)







この症状に対する質問
このような症状は何科で感知できますか?
匿名 様
コメントありがとうございます。
「このような症状は何科で完治できますか?」とのご質問についてですが、
申し訳ございません。
何科(医療機関)で完治できるかはわかりません。
しかし、鍼灸治療は効果が期待できます。
実際に当院にご来院された方で回復した方はおられます。
ぜひ、お近くの鍼灸院に通院されてみてはいかがでしょうか。
鈴木
実際にどこの医院に行くと良いのでしょうか?
別所克己 様
コメントありがとうございます。
「実際にどこの医院に行くと良いのでしょうか?」とのご質問についてですが、
当院にご来院されている患者様で比較的通院されている病院は、
東京科学大学病院歯科心身医療科に通院されている方が多いです。
ご参考になれば幸いです。
鈴木