
BLOG
ブログ
動悸で呼吸が浅い|息苦しい原因はストレス
- カテゴリ:
- 背中や腰の悩み
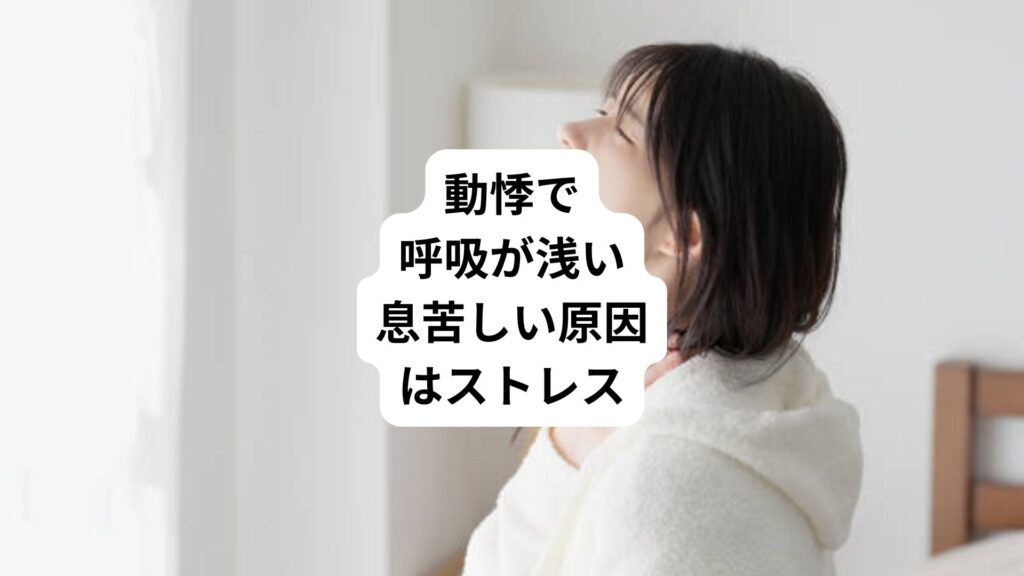
公開日:2024年07月10日
更新日:2025年08月07日
このブログを監修している鈴木貴之は国家資格であるはり師免許、きゅう師免許、柔道整復師免許、心理カウンセラーを取得した資格保有者です。
目次

息苦しさでお悩みの方に適切なアドバイス
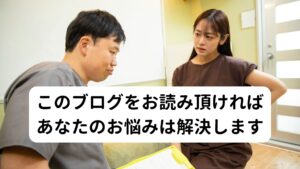
「胸が締め付けられるように息苦しさがある」
「急に心臓がバクバクとする動悸が起こる」
「動悸で呼吸が浅い」
「ストレスを感じると息苦しい」
このような不調を感じたら、仕事のストレスが原因の可能性があります。
息苦しさを初めとする身体症状は、比較的自覚しやすいストレス症状です。
しかし、そのままにしておくと、憂うつ感や意欲の低下、不眠などのより重い精神症状に発展していく可能性があります。
息苦しさはその前兆である心身からのSOSサインと捉え、適切に対処していくことが早期改善につながります。
今回は「動悸で呼吸が浅い|息苦しい原因はストレス」と題して、ストレスによって起こる息苦しさの原因や治し方について解説します。
また仕事をするうえで意識すべきポイントもまとめています。
息苦しい症状でお悩みの人はぜひご参考にしていただければと思います。
仕事のストレスで息苦しくなる要因に何があるか?
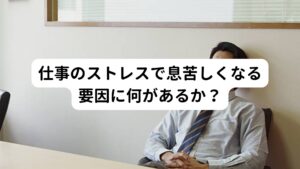
ストレスから息苦しさを感じる場合、どのような原因が考えられるでしょうか。
主な原因には自律神経の乱れや強い不安・緊張、ストレスへの不適応などがあります。
しかし、以下の3つの原因以外からも起こる場合や、様々な原因が複合的に生じた場合もあるため注意が必要です。
原因①:自律神経が乱れている(自律神経失調症)
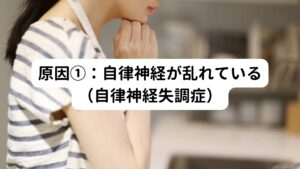
自律神経が乱れると息苦しさを感じやすくなります。
自律神経とは、人間の生命活動に必要な体温調節や消化機能の調節などを行う役割を果たしています。
例えば、部屋の温度が暑いと汗を分泌させて上昇する体温を下げようと働くように、身体の様々な機能を一定のバランスに保つ働きをすることが特徴です。
この自律神経の機能が乱れると呼吸にも悪影響が及びます。
自律神経が身体の機能のバランスを保つためには、活動時に活性化する交感神経と、休息時に活性化する副交感神経の2つの機能を調整する必要があります。
しかし、ストレスが慢性化すると交感神経が活発に活動する状態が続いてしまい、呼吸が浅く早くなったり、喉が詰まった感覚や息苦しさが生じることがあります。
原因②:強い不安感や過度な緊張が続いている(過呼吸・不安障害)
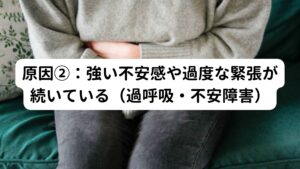
交感神経の活性化に加えて、強い不安感や過度な緊張が続くと、激しい息苦しさが出現することがあります。
不安感や緊張した状態では、無意識のうちに頻回に強く息を吸ったり吐いたりしてしまうため過呼吸が起きやすい傾向があります。
この過呼吸状態になると、体内の二酸化炭素濃度のバランスが崩れ、頭痛やめまい、けいれんなどの症状(テタニー)が起きることがあります。
また生じる症状に対しても強い不安感をおぼえて、より呼吸が激しくなり、さらに息苦しくなるといった悪循環に陥ることもあります。
また、不安障害やパニック障害など過度な不安が特徴の精神疾患でも、この過呼吸が起きやすいといえます。
交感神経によって引き起こされる息苦しさが、不安や緊張によってエスカレートしてしまうこともあります。
原因③:ストレスに適応できない(適応障害)
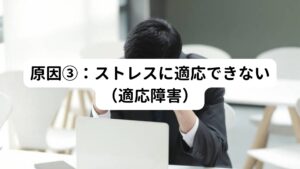
適応障害とは環境によるストレスが原因で様々な精神症状が起こる疾患です。
適応障害でも息苦しさや動悸が起こるケースは少なくありません。
この適応障害は現在の職場や業務内容への不適応により起きやすい傾向にあります。
例えば、以下のような場合はストレスが過度になりやすいといえるでしょう。
【①性格や特性が仕事に合っていない場合】
→内向的な性格なのに営業部門へ異動になった
【②周囲のサポートが得られない】
→上司や同僚は忙しそうで声をかけづらい
【③業務の裁量権がなく業務量も多い】
→上司からの修正が多く、残業しないと終わらない
ストレス以外で起こる息苦しさにも注意が必要
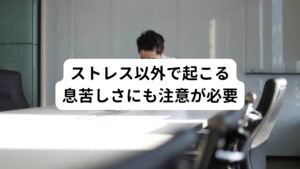
ストレス以外で生じる、身体疾患が原因の息苦しさの症状にも注意することが大切です。
例えば、狭心症や不整脈などの心疾患、気管支喘息や気管支炎などの呼吸器疾患によって息苦しくなる場合があります。
まずは息苦しさの原因がストレスだと決めつけず、内科で相談し検査を受けることが大切です。
検査の結果、身体的に異常がないと分かればおおよそストレスが原因である可能性が高いといえるでしょう。
仕事で実践したい7つの予防と対処法

では、このストレスで起こる息苦しさを対処、予防するにはどのような方法が良いのでしょうか。
今回は仕事の場面においての対処法を解説します。
【対処法①:業務量を調整する】
業務量は仕事上のストレスとして最もよくみられる要因です。
厚生労働省の調査では、業務量に対して強い負担(ストレス)を感じる労働者の割合が最も多いことが分かっています。
そのため業務量に負担を感じている場合は、上司に調整を相談するか、効率化を図る方法を考えるようにしましょう。
参考:厚生労働省「令和3年 労働安全衛生調査」(PDF)
【対処法②:適宜休息をとる】
自律神経の乱れや過度な不安感や緊張によって息苦しさを感じている人は、疲れやすく身体が回復しにくい傾向にあることがわかっています。
そのため息苦しさを少しでも感じたら、意識的に休憩を取ることが必要といえます。
仕事の合間であれば5~10分程度の休憩を取ったり、ときには半休を取得したりするなど、積極的に休息をとって心身のバランスを保つよう意識するようにしましょう。
【対処法③:出勤時間を変更する】
出勤がストレスの原因になっている場合は出勤時間の変更を申し出ることも良いでしょう。
例えば、通勤時間が長かったり、混雑する時間帯では満員電車などで不安感が高まり電車に乗りにくかったりするときが申し出るタイミングといえます。
その他にもリモートワークの割合を増やし、出社を減らすことも重要です。
【対処法④:産業医に相談する】
業務量の調整や休暇の取得、出勤時間の変更といった希望は、なかなか周囲の理解が得られないことがあります。
その場合は産業医に相談し、就業上の配慮が必要かどうかを判断してもらうことで周囲の理解を得やすくなります。
また必要があれば、現在の症状や必要な配慮について、代わりに産業医から上司に説明してもらうことも可能です。
産業医は中立的な立場であり、相談した内容は個人情報保護の観点から従業員の同意なしに会社に共有されることはありません。
そのため、安心して相談できます。
【対処法⑤:精神科・心療内科を受診する】
息苦しさの程度が強く、仕事に支障をきたしている場合は、精神科や心療内科にて適切な治療が必要な場合があります。
産業医は、あくまでも「業務変更や休職などの配慮が必要なレベルかどうか」を判断する役割を担う職務です。
そのため実際の症状に対する治療は医療機関の受診が必要です。
不安が強く息苦しくなっている場合は、医師との相談のうえ薬を処方し服用することで症状の緩和が期待できます。
受診までのハードルは高いこともありますが、医師の診察を受けるだけでも身心の状態が客観的に理解でき安心につながります。
【対処法⑥:リラックス方法を身につける】
自分の体質に合ったリラックス方法を身に付けることも、不安感や緊張を和らげ、息苦しさの解消につながります。
手軽にできるリラックス方法として、筋弛緩法があります。
筋弛緩法は身体の各部位に一度力を入れて一気に力を抜くということを繰り返すリラクゼーション法です。
10秒間力を入れて、その後15~20秒間脱力するということを繰り返します。
手足や背中、肩、顔など各部位に繰り返し行います。
どこにいても手軽にできるリラクゼーション法なので、不安や緊張をすぐに和らげたいときに最適です。
参考:厚生労働省「在外教育施設安全対策資料【心のケア編】第2章こころのケア各論」
【対処法⑦:ストレス対処力を高める】
ストレスへの反応として息苦しさが生じている場合には、対処力を高めてストレス自体を軽減することも有効です。
ストレスへの対処行動をコーピング(認知行動療法のひとつ)と呼びますが、自分に適したコーピングを選んで実行していくことが大切だといえます。
具体的には、ストレスの原因を取り除いたり、視点を切り替えたりすることにより、ストレスに対処することを目指します。
例えば、「ミスをした」という嫌な出来事に対して「好きな物を食べて発散する」「失敗から学べたと前向きに考える」などの対処が考えられます。
コーピングは有効なレパートリーが多ければ多いほど効果を発揮します。
効果を発揮させるためにも日頃から、「自分はどのようにストレスに対処しているか?」を詳しく見直していくことが大切です。
ストレスによる息苦しさは鍼灸治療で改善できます
このようなストレスによる息苦しさや呼吸の浅さの症状は当院の鍼灸治療で改善できます。
鍼灸治療は息苦しさの原因である自律神経の乱れを正常に戻す効果が期待できます。
また息がしにくい原因である呼吸に関わる筋肉の緊張を緩和させる効果もあるため呼吸自体も楽になりリラックス効果が高まります。
ぜひ、ストレスによる息苦しさでお悩みの方は当院にご相談ください。
当院で患者様の治療実績はこちらから
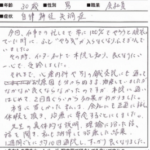
実際に当院ご来院になって改善された患者様の声と改善までの経過を報告します。
同じようにつらい思いをされている方の役に立てるのならばと皆さん快く掲載を許可頂きました。
これを読まれている患者様のご参考になれば嬉しく思います。
下記のリンクから別ページでご覧ください。


鍼灸院コモラボ院長
ブログ管理・編集者
鈴木貴之(すずきたかゆき)
【国家資格・所属】
鍼灸あんまマッサージ指圧師、柔道整復師、心理カウンセラー、メンタルトレーナー 治療家歴14年、日本東方医学会会員、脈診臨床研究会会員
神奈川県の鍼灸整骨院にて15年勤務(院長職を務める)
【施術経過の同意について】
本ブログに掲載する施術の経過の情報は「私は本施術の経過を匿名化して貴院のウェブサイトに掲載することに同意します。」と患者様から同意書を得ております。また氏名・連絡先は公開されません。
【医療受診の案内と施術の注意点】
次の症状がある場合は速やかに医療機関を受診してください。強い胸痛、意識障害、急激な症状の悪化、高熱、持続する出血。鍼灸・整体は有益ですが、抗凝固薬服用中、出血傾向、妊娠初期、感染症の疑いがある方は施術前に必ず医師へ相談してください。
現在、JR三鷹駅北口に自律神経専門の鍼灸院コモラボにて様々な不調の患者様に鍼灸治療を行っている。
【SNS】
Youtube , Instagram , X(Twitter)







この症状に対する質問