
BLOG
ブログ
胸に物が詰まった感じ|ストレスで食べ物が下がっていかない
- カテゴリ:
- 胸やお腹の悩み
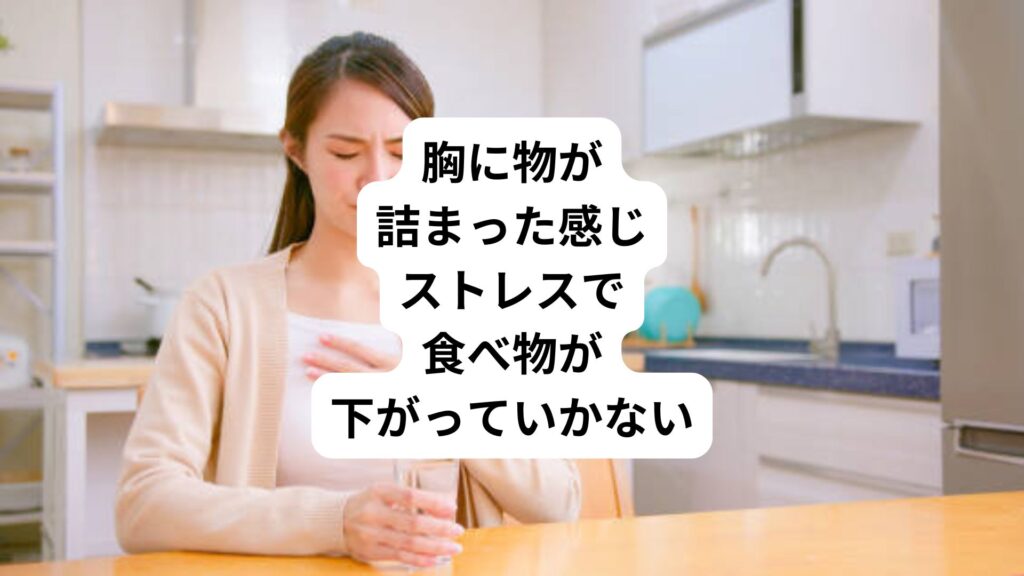
公開日:2025年07月25日
更新日:2025年07月25日
このブログを監修している鈴木貴之は国家資格であるはり師免許、きゅう師免許、柔道整復師免許、心理カウンセラーを取得した資格保有者です。
目次
- 1 食べ物がのどに詰まる原因を解説します
- 2 食べ物が下がっていかない症状の具体的な症状ついて
- 3 一つでも当てはまる場合は治療を開始しましょう
- 4 のどがつまる、食べ物が下がっていかないという症状の病気について
- 5 逆流性食道炎(びらん性胃食道逆流症)
- 6 非びらん性胃食道逆流症
- 7 ①機能性胸やけ
- 8 ②逆流性知覚過敏
- 9 機能性ディスペプシア
- 10 カンジダ食道炎
- 11 ウイルス性食道炎(サイトメガロウイルス食道炎、ヘルペスウイルス食道炎)
- 12 食道アカラシア
- 13 薬剤性食道炎
- 14 好酸球性食道炎
- 15 進行食道がん
- 16 バレット食道がん(食道胃接合部がん)
- 17 進行胃がん
- 18 咽頭がん
- 19 咽喉頭異常感症
- 20 虚血性心疾患(狭心症、心筋梗塞)
- 21 食べ物が下がっていかないなどの症状が出たときはどうする?
- 22 咽喉頭異常感症は東洋医学の鍼灸で改善できる
- 23 当院で患者様の治療実績はこちらから
- 24 関連する記事

食べ物がのどに詰まる原因を解説します
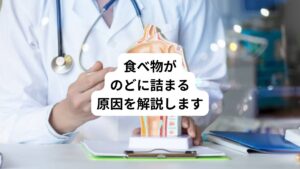
「食べ物がのどや胸でつまる感じがする」
「食べ物がのどや胸で引っかかって下がっていかない」
このような経験はないでしょうか。
不調が起きても水を飲んだり、時間が経つと症状が改善するからといって安心したり、様子を見たりしていないでしょうか。
これらの症状は、大きな固い食べ物をしっかり噛まずに丸呑みすることでも出ることがある症状です。
その場合、食道に何か原因があり出ている症状の可能性もあります。
自己判断で様子を見ずにまずは消化器内科を受診し、その原因を調べてもらいましょう。
今回は「胸に物が詰まった感じ|ストレスで食べ物が下がっていかない」と題して、どういった疾患が疑われるかについて解説します。
食べ物が下がっていかない症状の具体的な症状ついて
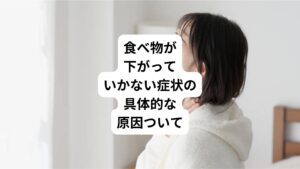
以下のような症状がある場合は何らかの不調が身体に起きている可能性があります。
・食事中や食後に喉に何かへばりつく違和感や詰まりがある
・食べ物が大きいと飲み込みにくい
・食べ物を飲み込むときにのどや胸にひっかかる感じがある
・食事中や食後に胸に食べ物がつまっているような感じがする
・食事を飲み込んだ後に水を飲まないとのどや胸でつかえる感じがする
・食べ物が飲み込んでも下がっていかない感じがある
・精神的なストレスを感じているときに食事をすると飲み込みにくい感じがする
・胸や背中に圧迫されるような痛みがある
・食事を食べると下がっていかない感じがあり吐いてしまう
・みぞおちが重苦しい感じがする
・ゲップが良く出る
一つでも当てはまる場合は治療を開始しましょう
症状の感じ方は、人により個人差がかなりあります。
あくまでも上記の具体例は、症状の一例です。
診察のときはご自身がつらいと感じている症状をそのままご自身の言葉で伝えて頂くのが最も大切です。
また「どういう時に症状が出現しやすいか」「症状を軽くしたり悪化させるものがあるか(姿勢や食事、行動や朝・昼・夜の時間で症状が変わるかなど)」といった具体的な特徴があれば伝えるようにしましょう。
のどがつまる、食べ物が下がっていかないという症状の病気について
ここからは「のどがつまる」「食べ物が下がらない」という症状の考えられる病気について解説します。
逆流性食道炎(びらん性胃食道逆流症)
胃酸が食道に逆流し、食道の粘膜にびらんや潰瘍などの炎症を来す疾患です。
胸やけ、呑酸症状の原因として最も多い疾患です。
そのため、炎症によってのどがつまる症状や食事が胸でつかえるような症状も出ることがあります。
炎症がひどい場合は出血を来すこともあります。
胃内視鏡検査(胃カメラ)で食道粘膜の炎症を確認することで診断ができます。
非びらん性胃食道逆流症
次の2つに分類されます。
いずれもストレスや不安、不眠などが原因です。
そのため胃内視鏡検査(胃カメラ)を行っても食道粘膜には炎症を認めません。
①機能性胸やけ
食道への胃酸逆流が無いにもかかわらず、胸やけ症状を認める疾患です。
ストレスや不安による食道の知覚過敏に加え、食道の動きが過剰に強くなっていることが原因といわれています。
のどがつまる症状や食事が胸でつかえるような症状が起こります。
②逆流性知覚過敏
胃酸の逆流は少量でも繰り返されることで食道粘膜が知覚過敏になります。
そのため少量の胃酸の逆流でも強い症状を感じることがあります。
のどがつまる症状や食事が胸でつかえるような症状も逆流性知覚過敏で起こります。
機能性ディスペプシア
症状の原因となる器質的疾患が無いにもかかわらず、3ヶ月以上継続する食後のもたれ感、胃が痛い、むかつきなどの症状が続き、日常生活に影響を来す疾患が機能性ディスペプシアです。
のどがつまる症状や食事が胸でつかえるような症状も出ることがあります。
根本的な原因にはストレスや不安などによる胃の知覚過敏と胃の運動機能障害が関係しているといわれています。
カンジダ食道炎
喘息に対するステロイド吸入剤や慢性的な酸逆流が原因で食道粘膜に真菌感染による食道炎を来す疾患です。
・胸やけ
・胸の違和感
・食事がつかえる
・食事が下がっていない
以上のような症状を感じることがあります。
のどがつまる症状も出ることもあります。
ウイルス性食道炎(サイトメガロウイルス食道炎、ヘルペスウイルス食道炎)
慢性炎症や免疫力の低下があるとサイトメガロウイルスやヘルペスウイルスによるウイルス感染で食道炎を来すことがあります。
逆流性食道炎と同様に胸やけや胸あたりの違和感、食事がつかえる、食事が下がっていないなどの症状を感じることがあります。
のどがつまる症状も出ることもあります。
食道アカラシア
食道下部の筋層内の神経の異常が原因で食道の運動障害や食道と胃のつながり目の弛緩不全(しまりが強い)を来します。
食べ物が通過しづらくなったり、食道が広がってしまって、のどや胸のつかえ感や嘔吐が主な症状としてでてきます。
胸やけ、呑酸、胸部不快感も認めることもありますが、食事がのどや胸でつかえる・下がっていないなどの症状が中心です。
また、精神的なストレスを感じているときや冷たい水などをとった時に症状が悪化しやすいのも特徴です。
薬剤性食道炎
十分な水分を摂取せずに薬を服用すると薬剤が食道に停滞し食道炎を来すことがあります。
以下の薬物が副作用が起こりやすいとされています。
・テトラサイクリン系の抗菌薬
・抗炎症薬
・カリウム製剤
・キニジン
・ビスホスホネート製剤
ひどくなると食道炎から食道潰瘍になることもあり、胸のあたりに痛みが強くでることもあります。
胸やけや胸あたりの違和感、食事がのどや胸でつかえる、食事が下がっていないなどの症状を感じることもあります。
好酸球性食道炎
食事などが原因で食道に慢性的なアレルギー性の食道炎を来す疾患です。
胸やけやゲップという症状がでることは少ないです。
・胸あたりのモヤモヤとした嫌な感じ
・胸やけ
・胸の違和感
・食事がのどや胸でつかえる
・食事が下がっていない
以上の症状を感じることがあります。
進行食道がん
進行食道がんは、食道の空間を狭めるため、食事摂取時のつかえ感や胸やけ症状、胸痛などの症状が出現します。
習慣的に飲酒や喫煙、熱い飲み物を摂取する方は食道がんになりやすいと言われています。
心窩部痛(胃痛・みぞおちの痛み)や出血の原因となることもあります。
食道がんは咽頭がんとリスクファクターが同じであり食道がんがある場合は、咽頭がんも合併していることも比較的多くみられます。
咽頭がんがある場合は、のどがつまる症状も出ることもあります。
バレット食道がん(食道胃接合部がん)
食道と胃のつなぎ目である食道胃接合部に胃酸逆流による炎症が長年続くと、がんが出来ることがあります。
胃酸の逆流が続くことにより逆流性食道炎と同様に胸やけやゲップ、胸あたりの不快感を時々感じることがあります。
また、食事がのどや胸でつかえる・下がっていないなどの症状を感じることや心窩部痛(胃痛・みぞおちの痛み)や出血の原因となることもあります。
進行胃がん
進行胃がんが原因で胃の通過障害が出現したり、スキルス胃癌により胃が膨らむことが出来なくなると胃の内容物が食道に逆流しやすくなります。食事をした後に胃酸や食べ物が逆流することにより逆流性食道炎を起こすこともあります。
それにより胸やけや胸あたりのモヤモヤした嫌な感じがでることや食事がのどや胸でつかえる・下がっていないなどの症状を感じることがあります。
心窩部痛(胃痛・みぞおちの痛み)や出血の原因となることもあります。
咽頭がん
早期の咽頭がんはほとんど症状がありませんが、進行すると食事中や食後に喉に何かがくっついているような違和感やつまっている感じが出現することがあります。
食道がんと同じく習慣的に飲酒や喫煙、熱い飲み物を摂取する方は咽頭がんになりやすいと言われています。
咽頭がんがある場合は、食道がんも合併していることも比較的多くみられます。
咽喉頭異常感症
ストレスが原因で食道やのどの粘膜が知覚過敏の状態を来す状態をさします。
しかし、咽頭、喉頭や食道自体には炎症や腫瘍などの異常はありません。
以下の症状が起こります。
・のどがつまる感じ
・のどの違和感
・のどの異物感
・食道のつまる感じ
・食べ物がひっかかるような感覚
胃内視鏡検査(胃カメラ)をうけても何も異常が無い場合に診断されます。
検査で異常が無いことが分かるとそれだけで改善することも多くあります。
虚血性心疾患(狭心症、心筋梗塞)
階段を登ったり、小走りした時など動いたときに胸が重苦しい症状やつかえる感じが出現します。
休むと数分で改善する場合は、食道や胃ではなく心臓に問題がある場合もあります。
食べ物が下がっていかないなどの症状が出たときはどうする?
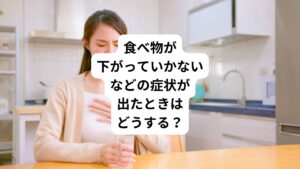
症状がある場合は、放置せずまずは消化器内科を受診しましょう。
食道がんや胃がんが隠れている場合があるだけでなく、逆流性食道炎、好酸球性食道炎や食道アカラシアといった治療が必要な疾患が原因のこともあります。
検査後、「特に異常がない」「原因不明」といった診断を受けて具体的な治療がない場合は鍼灸治療などが有効です。
薬物療法などの対処療法で治療が行き詰っている場合は鍼灸治療をご検討ください。
咽喉頭異常感症は東洋医学の鍼灸で改善できる
当院ではこのような喉に不調を起こす咽喉頭異常感症には西洋医学と東洋医学の両方の観点からアプローチをし改善を図ります。
まずは咽喉頭異常感症の原因である「喉の筋肉の緊張」として捉えて西洋医学的な観点で局所的な治療を喉に施します。
それにより喉の筋肉の緊張が緩和され呼吸がしやすくなります。
また根本的な原因である自律神経の乱れ、とくに交感神経の興奮を改善させるためには東洋医学的な観点で個々の体質をお調べし、体質にあった東洋医学のツボを利用して体質改善を図ることが重要です。
この西洋医学による局所的な治療と東洋医学による根本的な治療を組み合わせることで鍼灸の効果を最大限に引き出して咽喉頭異常感症の改善を図ります。
また当院では個々の患者様の体質を詳しくお調べし個々の体質にあった鍼灸治療を行うためマニュアル通りの治療ではない効果も引き出せます。
ぜひ、咽喉頭異常感症でお悩みの方は当院にご相談ください。
当院で患者様の治療実績はこちらから
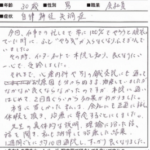
実際に当院ご来院になって改善された患者様の声と改善までの経過を報告します。
同じようにつらい思いをされている方の役に立てるのならばと皆さん快く掲載を許可頂きました。
これを読まれている患者様のご参考になれば嬉しく思います。
下記のリンクから別ページでご覧ください。


鍼灸院コモラボ院長
ブログ管理・編集者
鈴木貴之(すずきたかゆき)
【国家資格・所属】
鍼灸あんまマッサージ指圧師、柔道整復師、心理カウンセラー、メンタルトレーナー 治療家歴14年、日本東方医学会会員、脈診臨床研究会会員
神奈川県の鍼灸整骨院にて15年勤務(院長職を務める)
【施術経過の同意について】
本ブログに掲載する施術の経過の情報は「私は本施術の経過を匿名化して貴院のウェブサイトに掲載することに同意します。」と患者様から同意書を得ております。また氏名・連絡先は公開されません。
【医療受診の案内と施術の注意点】
次の症状がある場合は速やかに医療機関を受診してください。強い胸痛、意識障害、急激な症状の悪化、高熱、持続する出血。鍼灸・整体は有益ですが、抗凝固薬服用中、出血傾向、妊娠初期、感染症の疑いがある方は施術前に必ず医師へ相談してください。
現在、JR三鷹駅北口に自律神経専門の鍼灸院コモラボにて様々な不調の患者様に鍼灸治療を行っている。
【SNS】
Youtube , Instagram , X(Twitter)

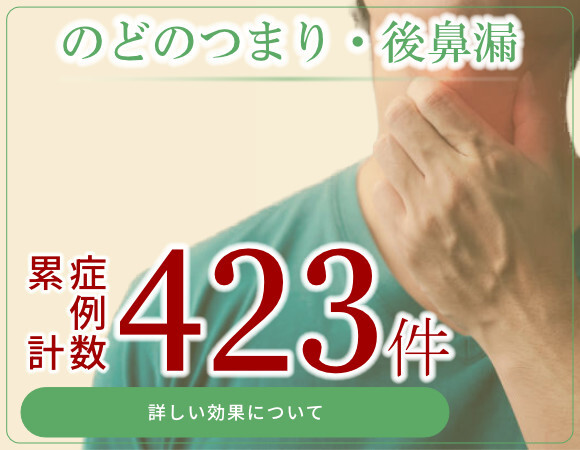





この症状に対する質問