
BLOG
ブログ
コーヒーで焦燥感|カフェインで起こる不安感の対処法
- カテゴリ:
- 全身のお悩み
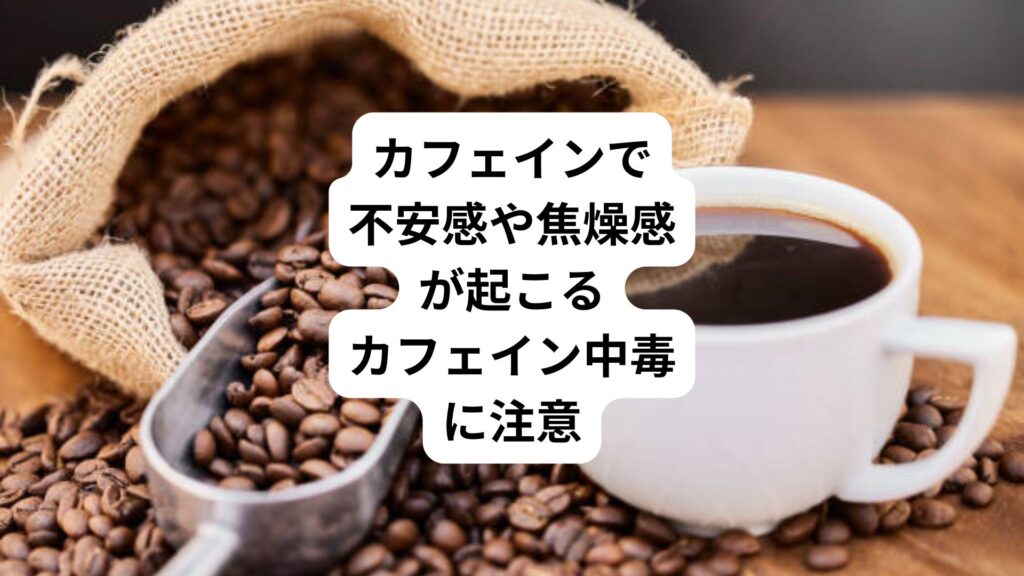
公開日:2025年04月23日
更新日:2025年10月03日
このブログを監修している鈴木貴之は国家資格であるはり師免許、きゅう師免許、柔道整復師免許、心理カウンセラーを取得した資格保有者です。
目次
- 1 カフェインの摂りすぎについて解説します
- 2 カフェインは中枢神経系を興奮させる
- 3 カフェインが含まれるもの
- 4 カフェインの適量は一日400㎎未満
- 5 カフェインの摂りすぎで起こる中毒症状とは
- 6 カフェインの過剰摂取による症状について
- 7 カフェインの副作用を抑えるためには
- 8 カフェイン断ちは減らすか完全にやめるかしかない
- 9 1. 1日の摂取量を把握する
- 10 2. 段階的に減量する
- 11 3. コーヒーの代わりにデカフェやハーブティーにする
- 12 4. 質の高い睡眠をとるようにする
- 13 カフェインの過剰摂取による不調でお悩みの方はご相談ください
- 14 カフェインによる不安感や焦燥感【41歳女性 会社員(神奈川県在住)】
- 15 関連する記事
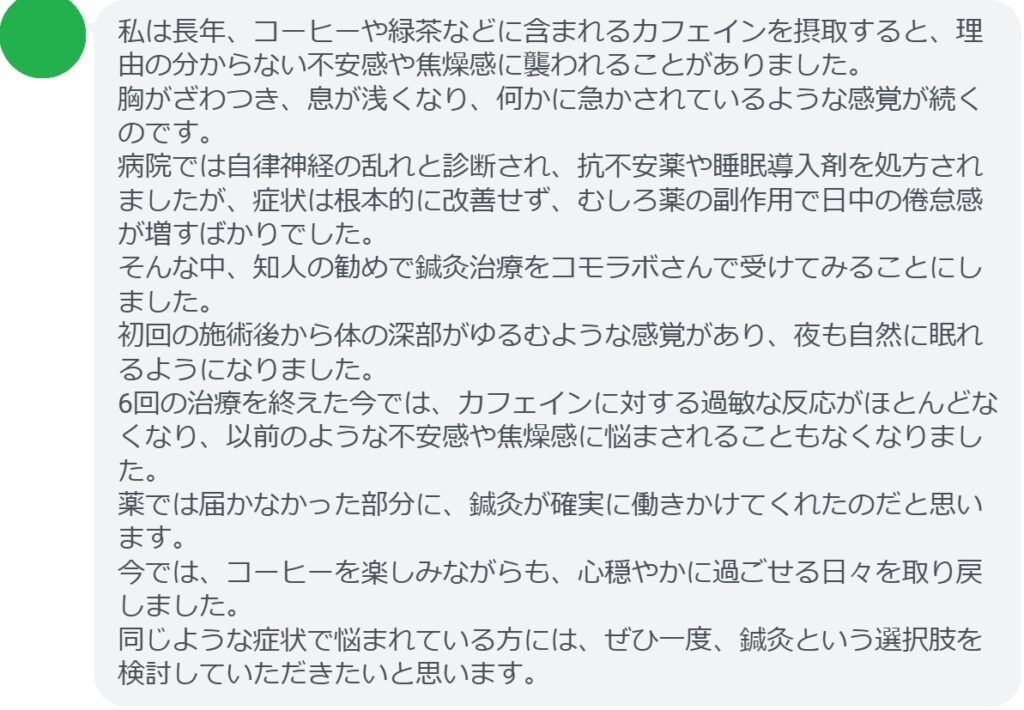
カフェインの摂りすぎについて解説します

日ごろコーヒーは多くの人にとって日常的な飲み物です。
いつでもコンビニや専門店などで容易に美味しいコーヒーを楽しむことができます。
しかし、コーヒーを飲むことが習慣的になるとコーヒーに含まれるカフェインを摂りすぎになってしまいます。
今回は「コーヒーで焦燥感|カフェインで起こる不安感の対処法」と題してカフェインの摂りすぎについて解説します。
カフェインは中枢神経系を興奮させる
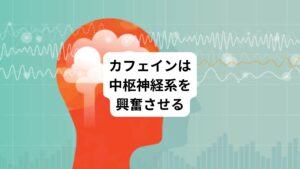
カフェインは、コーヒー、紅茶、緑茶、コーラなどの飲料に含まれる自然発生する刺激物です。
カフェインは主に中枢神経系を刺激し、一時的に疲労感を減らし、覚醒度を高める作用があります。
摂取すると、集中力が向上したり、気分が高揚することがあります。
そのため過剰に摂取すると不安感や不眠などの副作用が現れることがあります。
※体質によってカフェインに対する感受性は異なるため、適量は個人によって異なります。
カフェインが含まれるもの

カフェインはコーヒー豆やカカオ豆、茶葉などに天然に含まれています。
コーヒーや茶がカフェインの主要な摂取源となっています。
また、エナジードリンクや清涼飲料水、風邪薬、眠気防止薬、酔い止め薬などにもカフェインが含まれていることがあります。
以下は代表的な食品中のカフェイン濃度です(100mlあたり)
・エナジードリンク又は眠気覚まし用飲料: 32~300 mg
・コーヒー(浸出液): 60 mg
・インスタントコーヒー(粉末): 80 mg
・玉露(浸出液): 160 mg
・せん茶(浸出液): 20 mg
・ほうじ茶(浸出液): 20 mg
・玄米茶(浸出液): 10 mg
・ウーロン茶(浸出液): 20 mg
・紅茶(浸出液): 30 mg
・抹茶(粉末): 48 mg
カフェインの適量は一日400㎎未満
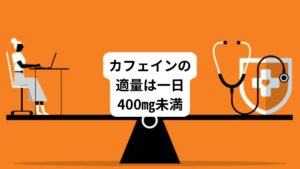
カフェインは過剰摂取すると上で述べたように不調を引き起こす可能性があります。
カフェインに対する耐性は個人差がありますが、一般的には一日の摂取量は400㎎未満に止めることが推奨されています。
ヨーロッパなどの基準では一回の摂取で200㎎以上の摂取は控えるべきとの提言もあります。
とくに一度に大量のカフェイン摂取は避けるようにし、こまめに摂ることが好ましいと考えられています。
カフェイン400㎎はおおよそコーヒー4~5杯、紅茶では7~8杯ほどの量に相当します。
しかし、カフェインは食品や薬にも含まれていることもあります。
そのため一日に摂取する総量は食事なども含めて考えて調節しましょう。
カフェインの摂りすぎで起こる中毒症状とは

カフェインの過剰摂取は、いくつかの不快な症状や健康問題を引き起こす可能性があります。
摂取量が多いと感じる場合、以下のような症状が現れることがあります。
カフェインの過剰摂取による症状について
【不安感】
カフェインは中枢神経系を刺激します。
過剰に摂取すると不安感や神経質になることがあります。
【心拍数の増加】
心拍数が速くなったり、不整脈が発生します。
【睡眠障害】
カフェインは交感神経の興奮を高めます。
そのため睡眠時に必要な副交感神経が働きにくくなります。
また長期間カフェインを過剰摂取すると、不眠症などの睡眠障害を引き起こすこともあります。
【胃腸機能の障害】
胃痛、胃酸過多、下痢など消化器系に影響を及ぼすことがあります。
【頭痛】
カフェインは血管を一時的に収縮させる効果があります。
この血管が収縮することで血流を悪くなり頭痛が起こります。
さらにカフェインが体内から抜けると、収縮した血管は一気に拡張し元に戻ります。
この収縮から解放されて起こる血流量の増加も頭痛の原因となります。
【疲労感】
カフェインには疲労解消の効果があるといわれています。
しかし、これは実際に疲労感が解消されているわけではなく脳が疲労を感じにくくなっているだけです。
そのためカフェインが体内から抜けると一気に疲労を感じるようになります。
この反応はカフェインに含まれるアデノシンという成分には覚醒作用によるものです。
【貧血】
カフェインは、鉄の吸収を阻害したり、タンニンと結びついたりします。
そのため鉄欠乏性貧血を引き起こすことがあります。
【その他】
震え、落ち着きがなくなる、焦燥感を感じる
カフェインの副作用を抑えるためには
【水分を摂る】
カフェインの過剰摂取により起こる症状は、水分を補給することで緩和できます。
【カリウム・マグネシウムの摂取】
カリウム・マグネシウムの摂取することもカフェインの副作用を抑えることに役立ちます。
これはカフェインの過剰摂取でカリウムやマグネシウムが消費されると、震えやイライラなどの症状が起こることがあるからです。
コーヒーを飲み過ぎたときには、バナナや濃い葉物野菜などを食べて、カリウムやマグネシウムを補給しましょう。
カフェイン断ちは減らすか完全にやめるかしかない
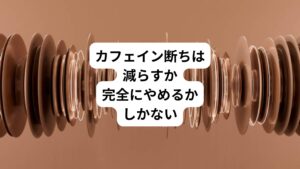
カフェインを断つためには、カフェイン摂取を減らすか、完全に止めることしかありません。
以下のような問題がある場合はカフェイン断ちを行うことをおすすめします。
・健康上の懸念
・不眠症
・不安感の増加
・依存からの解放
カフェイン断ちをする際には、以下の点に注意すると良いでしょう。
1. 1日の摂取量を把握する
カフェイン断ちをする前に、日々の摂取量を把握することが大切です。
なかには「飲み終わったらまたコーヒーを淹れて飲んで・・・」を繰り返して、1日何杯コーヒーを飲んでいるのかわからないという方もいるかもしれません。
まずは1日にコーヒーを何杯飲んでいるかカウントして、自分の摂取量を把握しましょう。
2. 段階的に減量する
これまでカフェインを過剰に摂取していた人が、いきなりカフェインを完全に断つと、離脱症状が強く出る恐れがあります。
通常は24〜48時間以内に離脱症状が現れることがあります。
以下のような症状がでたら離脱症状の可能性があります。
・頭痛
・疲労感
・イライラ
・集中力の低下
・うつ症状
これらの症状は一般的に数日から一週間程度続きます。
この様な症状が強く出ないように段階的に減量していくようにしましょう。
今まで1日に5杯コーヒーを飲んでいた方は、まずは3杯に。
翌週は2杯、その翌週は1杯だけ……と徐々に減らしていくようにします。
このような段階的な減量であれば離脱症状も穏やかになり、少ない負担でカフェイン断ちができるようになります。
3. コーヒーの代わりにデカフェやハーブティーにする
「コーヒーが飲めなくて辛い」という方は、デカフェ(カフェインが入っていないコーヒー)やハーブティーを代わりに飲んでみてはいかがでしょうか。
最近はデカフェでもコーヒーの香りや味わいが楽しめる製品がたくさんあります。
食後の口直しや作業中に一息つきたいときなどにコーヒーを飲んでいた方の場合は特に、デカフェやハーブティーでも十分その役割を果たしてくれます。
4. 質の高い睡眠をとるようにする
カフェイン断ちの期間は、質の良い睡眠を取ることが特に重要です。
また、ストレス解消法(瞑想、ヨガ、軽い運動など)を取り入れると、撤退症状の軽減に役立つ場合があります。
カフェイン断ちを成功させるためには、自己観察と調整が重要です。
体がどのように反応するかを注意深く観察し、必要に応じてプロセスを調整することが、断ちをスムーズに進める鍵となります。
カフェインの過剰摂取による不調でお悩みの方はご相談ください
当院の鍼灸治療は脳の疲労や興奮状態を解消させ、自律神経のバランスを整え、ホルモンの働きを良くするために行います。
筋肉の緊張や血流障害などを調整し全身の血行循環を改善し不調を解消させます。
鍼灸によって自律神経やホルモンの働きをコントロールしている脳の中枢神経の働きを正常化することで、自律神経やホルモンバランスの乱れを解消します。
この施術を行うことで、カフェインの過剰摂取による自律神経やホルモンバランスの不調を解消させることができます。
ぜひ、カフェインの過剰摂取による不調でお悩みの方は当院にご相談ください。
カフェインによる不安感や焦燥感【41歳女性 会社員(神奈川県在住)】
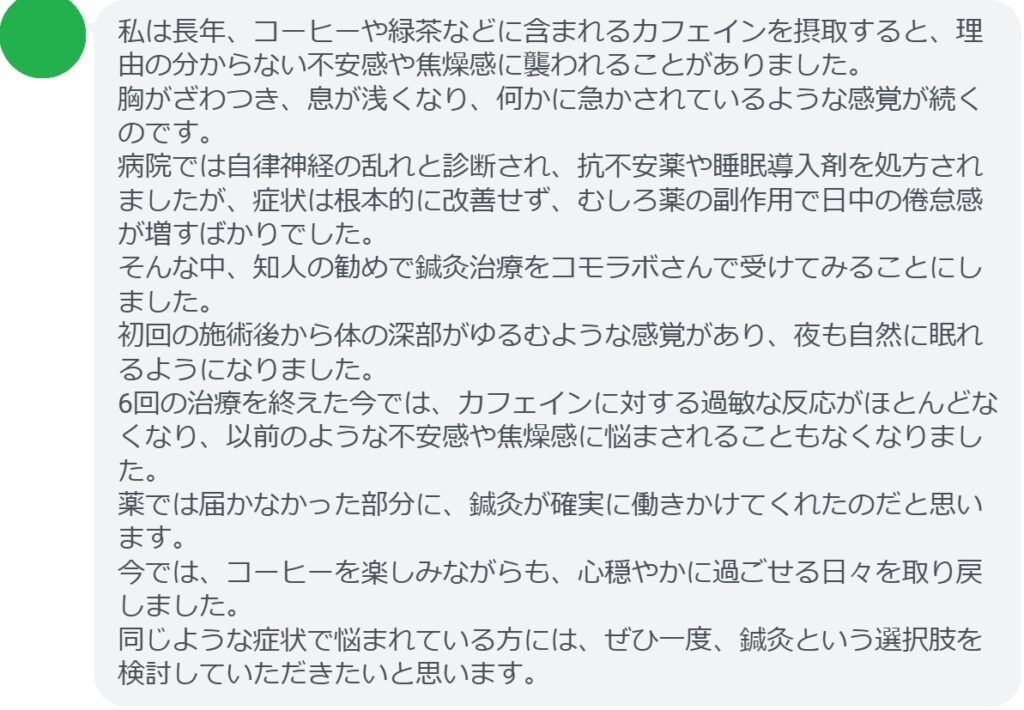
【カフェインによる不安感や焦燥感が改善された方の感想(口コミレビュー)】
・神奈川県在住/41歳女性
私は長年、コーヒーや緑茶などに含まれるカフェインを摂取すると、理由の分からない不安感や焦燥感に襲われることがありました。
胸がざわつき、息が浅くなり、何かに急かされているような感覚が続くのです。
病院では自律神経の乱れと診断され、抗不安薬や睡眠導入剤を処方されましたが、症状は根本的に改善せず、むしろ薬の副作用で日中の倦怠感が増すばかりでした。
そんな中、知人の勧めで鍼灸治療をコモラボさんで受けてみることにしました。
初回の施術後から体の深部がゆるむような感覚があり、夜も自然に眠れるようになりました。
6回の治療を終えた今では、カフェインに対する過敏な反応がほとんどなくなり、以前のような不安感や焦燥感に悩まされることもなくなりました。薬では届かなかった部分に、鍼灸が確実に働きかけてくれたのだと思います。
今では、コーヒーを楽しみながらも、心穏やかに過ごせる日々を取り戻しました。
同じような症状で悩まれている方には、ぜひ一度、鍼灸という選択肢を検討していただきたいと思います。
実際に当院ご来院になって改善された患者様の声と改善までの経過を報告します。
下記のリンクから別ページでご覧ください。


鍼灸院コモラボ院長
ブログ管理・編集者
鈴木貴之(すずきたかゆき)
【国家資格・所属】
鍼灸あんまマッサージ指圧師、柔道整復師、心理カウンセラー、メンタルトレーナー 治療家歴14年、日本東方医学会会員、脈診臨床研究会会員
神奈川県の鍼灸整骨院にて15年勤務(院長職を務める)
【施術経過の同意について】
本ブログに掲載する施術の経過の情報は「私は本施術の経過を匿名化して貴院のウェブサイトに掲載することに同意します。」と患者様から同意書を得ております。また氏名・連絡先は公開されません。
【医療受診の案内と施術の注意点】
次の症状がある場合は速やかに医療機関を受診してください。強い胸痛、意識障害、急激な症状の悪化、高熱、持続する出血。鍼灸・整体は有益ですが、抗凝固薬服用中、出血傾向、妊娠初期、感染症の疑いがある方は施術前に必ず医師へ相談してください。
現在、JR三鷹駅北口に自律神経専門の鍼灸院コモラボにて様々な不調の患者様に鍼灸治療を行っている。
【SNS】
Youtube , Instagram , X(Twitter)







この症状に対する質問