
BLOG
ブログ
拍動性耳鳴りの体験談|更年期の拍動性耳鳴りの治し方と知恵袋
- カテゴリ:
- 頭や顔の悩み
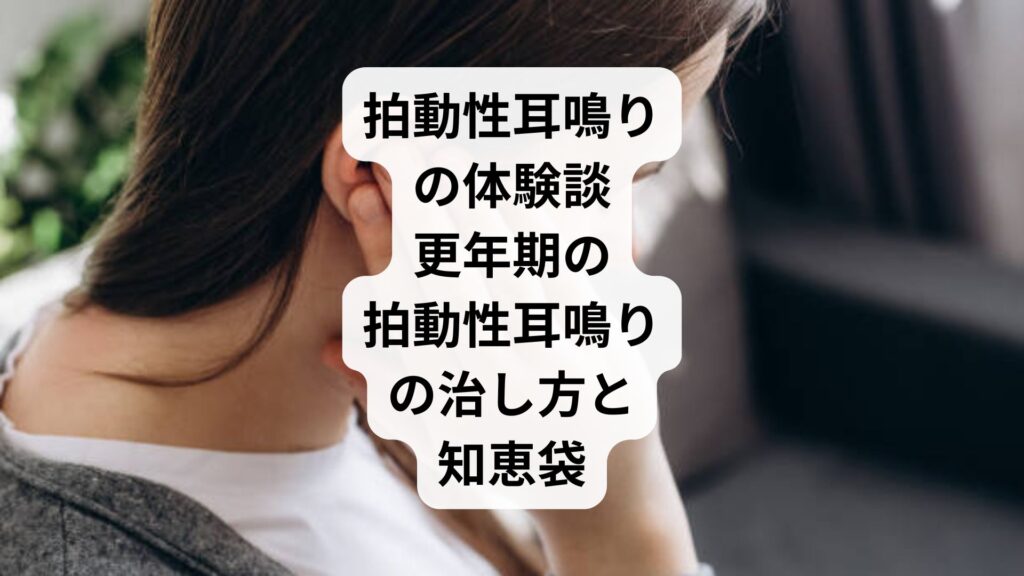
公開日:2024年08月13日
更新日:2025年09月25日
このブログを監修している鈴木貴之は国家資格であるはり師免許、きゅう師免許、柔道整復師免許、心理カウンセラーを取得した資格保有者です。
目次
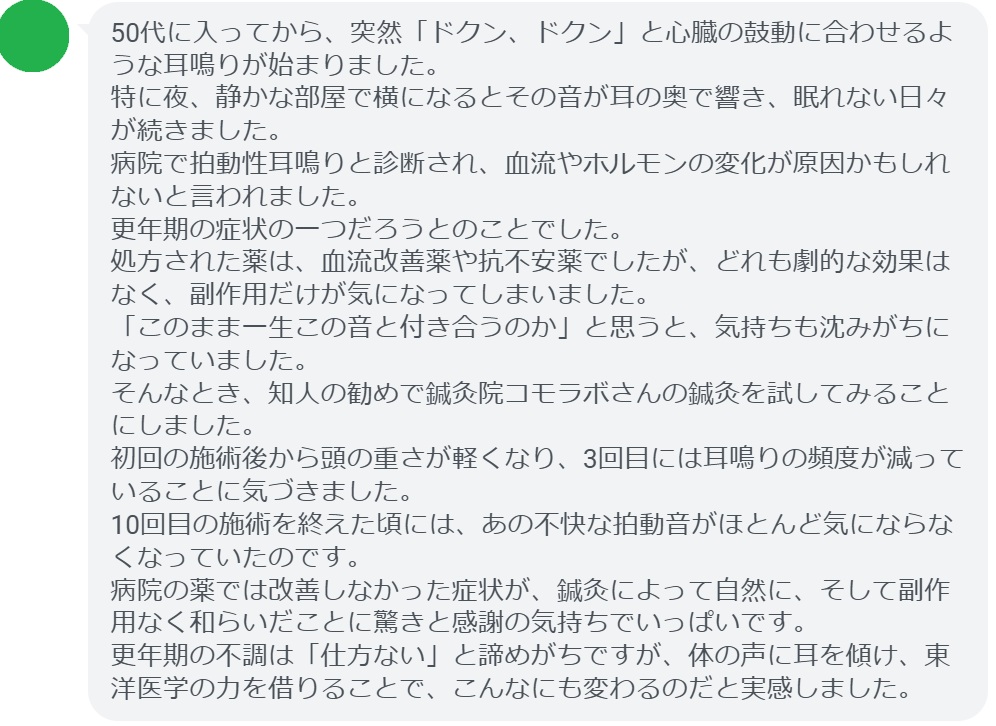
更年期に起こる耳鳴り症状でお悩みの方に適切なアドバイス
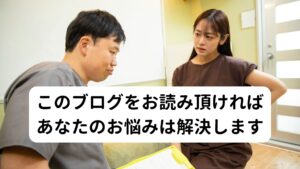
「ドクンドクン、ザーザーといった音が耳の奥で聞こえる」
「心臓の鼓動と同じリズムで音が聞こえる」
「夜になると耳鳴りが気になって眠れない」
「血液が流れるような音がする」
このような不調でお悩みの方はおられないでしょうか。
このような耳鳴りはとくに更年期に発生しやすいといわれています。
しかし、最近では若年層であっても症状がでる方が増えている印象です。
今回は「拍動性耳鳴りの体験談|更年期の拍動性耳鳴りの治し方と知恵袋」と題して更年期に起こりやすい拍動性耳鳴りの原因や症状について詳しく解説します。
拍動性耳鳴りが起こる原因について
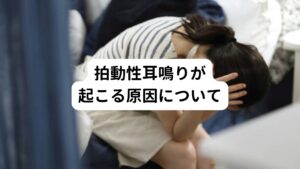
耳鳴りは耳や脳の問題がまず考えられます。
【耳に問題がある】
耳の中にある「蝸牛(かぎゅう)」は、音を脳に伝える役割があります。
その蝸牛に何らかの器質的な問題(腫れ、炎症、物理的な障害)があると、耳鳴りや難聴が起こりやすくなります。
また、補聴器の音の調節が合わない、耳垢が溜まっている、といったことでも音が正常に伝えられないために耳鳴りが起こることがあります。
【脳に問題がある】
耳に問題がなくても、音の情報を処理する脳に問題があっても耳鳴りを起こすことがあります。
その他には首や肩の筋緊張や、自律神経の乱れも耳鳴りの原因になると考えられています。
拍動性耳鳴りの症状について

更年期に起こりやすい拍動性耳鳴りは「ドクンドクン」といった血液が流れる脈拍の音など一定のリズムで起こる症状のものをいいます。
その他には「ザー」「ゴー」といった低音の耳鳴り、「キーン」「ピーン」といった金属音に似た高音の耳鳴りなどの症状も起こります。
日常生活でできる拍動性耳鳴り対策について
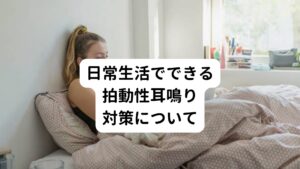
拍動性耳鳴りを改善、予防していくためには、日常でどのような点に気をつけていけば良いのでしょうか?
こちらでは「日常生活でおこなえる、耳鳴りとめまい対策」について詳しく解説します。
【首や肩まわりのストレッチ】
首や肩の緊張は、拍動性耳鳴りの原因の1つだと考えられます。
こまめにストレッチをおこない、首や肩の筋肉を柔らかくしておくことが大切です。
【ストレスをためない】
ストレスは自律神経を乱す大きな要因になると考えられています。
そのため趣味を楽しむ、適度に運動する、入浴するなどして、日常的に心身のストレスを発散するように心がけましょう。
【規則正しい生活を送る】
不規則な生活も自律神経が乱れる要因とされています。
起床時間や就寝時間など生活リズムを整えて固定し、規則正しい生活を送るように心がけましょう。
【医療機関に相談する】
拍動性耳鳴りやめまいの多くの原因は、脳が機能異常を起こしていることがわかってきました。
しかし、この症状は西洋医学では薬物療法による対処療法のみであり改善できません。
鍼灸や漢方など体質改善で治療する医療機関で相談しましょう。
拍動性耳鳴りに対する東洋医学的な考え
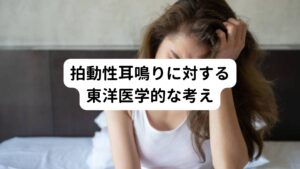
拍動性耳鳴りは東洋医学敵には全身の気(体全体を巡る生命エネルギー)や血の流れを改善し、自然治癒力を向上させることで改善できます。
この拍動性耳鳴りは、体内の体液(水分)の流れが滞り、体液のコントロールができにくくなっている状態です。
聴覚や平衡感覚を司る内耳に水が滞って溜まってしまうことで循環が悪くなり耳鳴りが起こると考えられます。
また東洋医学では耳鳴りが起こる左右の耳でも違いがあります。
左側の耳鳴りは気虚(気が足りない状態)によって起こる持続的な症状が特徴で、疲れたり冷えやのぼせると症状が強く起こります。
右側の耳鳴りは血虚(血液が足りない状態)と考え、音が大小変化し、断続的に鳴るのが特徴です。
当院最新の症例報告と知恵袋

【最新情報】
拍動性耳鳴りでお悩みの方は当院には多くご来院されています。
当院の統計ではありますが、拍動性耳鳴りでお悩みの方には共通したことがあります。
それは「のぼせやほてりがある」ということです。
東洋医学的に考えると「冷えのぼせ」という下肢の冷えや血行不良によって頭部に熱が溜まっている状態と考えられます。
その熱が体に悪さをして拍動性耳鳴りを引き起こしていると考えます。
そのため上昇した熱を足元に戻すために下肢を積極的に温めることが有効とします。
患者様にも「半身浴などでしっかり足を温めるようにしてください」とセルフケアを推奨すると「温めると耳鳴りがとまる」という反応があるそうです。
当院でも下肢の血流改善を目的とした鍼灸治療で改善率を高めています。
拍動性耳鳴りは東洋医学の鍼灸治療で改善できます
現在、当院では拍動性耳鳴りでお悩みの方が多くご来院されています。
拍動性耳鳴りは首こり・肩こりの緊張や自律神経の乱れが原因です。
そのため生活習慣で起こるストレスや過労が積み重なることで誰でも起こり、また再発もしやすいのが特徴です。
改善のためには首や肩の筋肉の緊張を緩めて血流を改善させることが重要であり、それができるのは鍼灸治療になります。
ぜひ、拍動性耳鳴りでお悩みの方は当院の鍼灸治療を受けてみてはいかがでしょうか。
更年期の拍動性耳鳴り【52歳女性 会社員(東京都在住)】
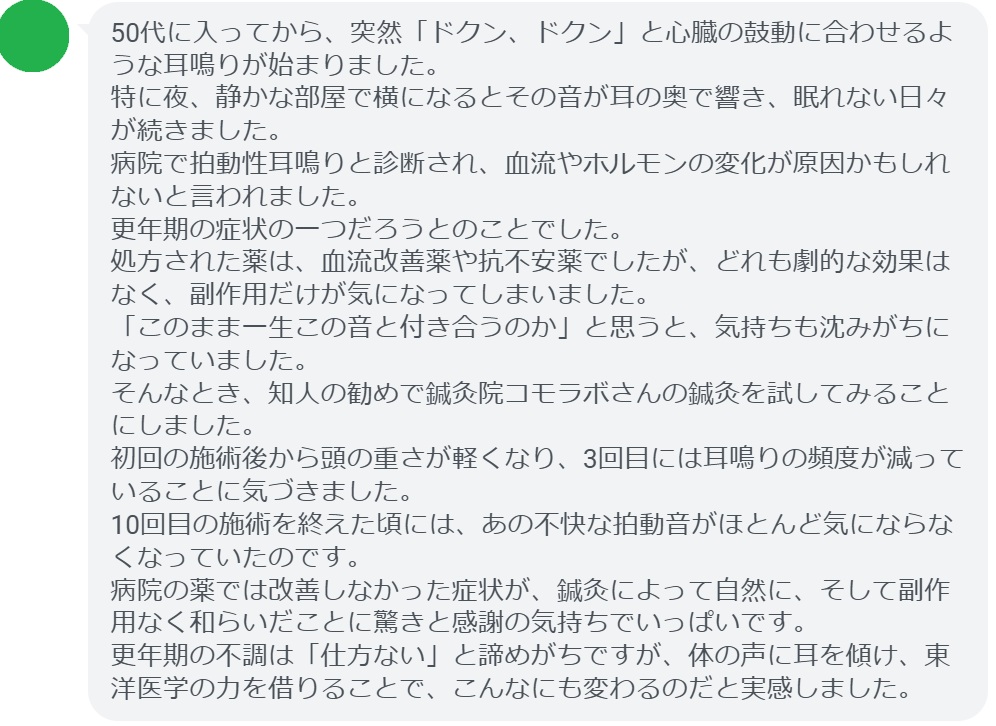
【更年期の拍動性耳鳴りが改善された方の感想(口コミレビュー)】
・東京都在住/52歳女性
50代に入ってから、突然「ドクン、ドクン」と心臓の鼓動に合わせるような耳鳴りが始まりました。
特に夜、静かな部屋で横になるとその音が耳の奥で響き、眠れない日々が続きました。
病院で拍動性耳鳴りと診断され、血流やホルモンの変化が原因かもしれないと言われました。
更年期の症状の一つだろうとのことでした。
処方された薬は、血流改善薬や抗不安薬でしたが、どれも劇的な効果はなく、副作用だけが気になってしまいました。
「このまま一生この音と付き合うのか」と思うと、気持ちも沈みがちになっていました。
そんなとき、知人の勧めで鍼灸院コモラボさんの鍼灸を試してみることにしました。
初回の施術後から頭の重さが軽くなり、3回目には耳鳴りの頻度が減っていることに気づきました。
10回目の施術を終えた頃には、あの不快な拍動音がほとんど気にならなくなっていたのです。
病院の薬では改善しなかった症状が、鍼灸によって自然に、そして副作用なく和らいだことに驚きと感謝の気持ちでいっぱいです。
更年期の不調は「仕方ない」と諦めがちですが、体の声に耳を傾け、東洋医学の力を借りることで、こんなにも変わるのだと実感しました。
実際に当院ご来院になって改善された患者様の声と改善までの経過を報告します。
下記のリンクから別ページでご覧ください。


鍼灸院コモラボ院長
ブログ管理・編集者
鈴木貴之(すずきたかゆき)
【国家資格・所属】
鍼灸あんまマッサージ指圧師、柔道整復師、心理カウンセラー、メンタルトレーナー 治療家歴14年、日本東方医学会会員、脈診臨床研究会会員
神奈川県の鍼灸整骨院にて15年勤務(院長職を務める)
【施術経過の同意について】
本ブログに掲載する施術の経過の情報は「私は本施術の経過を匿名化して貴院のウェブサイトに掲載することに同意します。」と患者様から同意書を得ております。また氏名・連絡先は公開されません。
【医療受診の案内と施術の注意点】
次の症状がある場合は速やかに医療機関を受診してください。強い胸痛、意識障害、急激な症状の悪化、高熱、持続する出血。鍼灸・整体は有益ですが、抗凝固薬服用中、出血傾向、妊娠初期、感染症の疑いがある方は施術前に必ず医師へ相談してください。
現在、JR三鷹駅北口に自律神経専門の鍼灸院コモラボにて様々な不調の患者様に鍼灸治療を行っている。
【SNS】
Youtube , Instagram , X(Twitter)

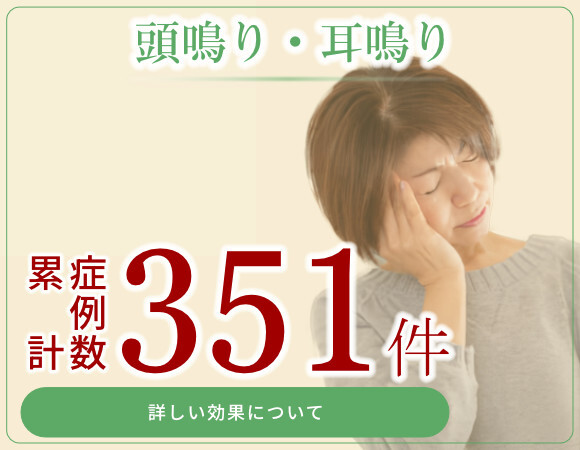





この症状に対する質問