
BLOG
ブログ
虚脱感とは|ストレスで急に体の力が抜ける自律神経失調症
- カテゴリ:
- 全身のお悩み
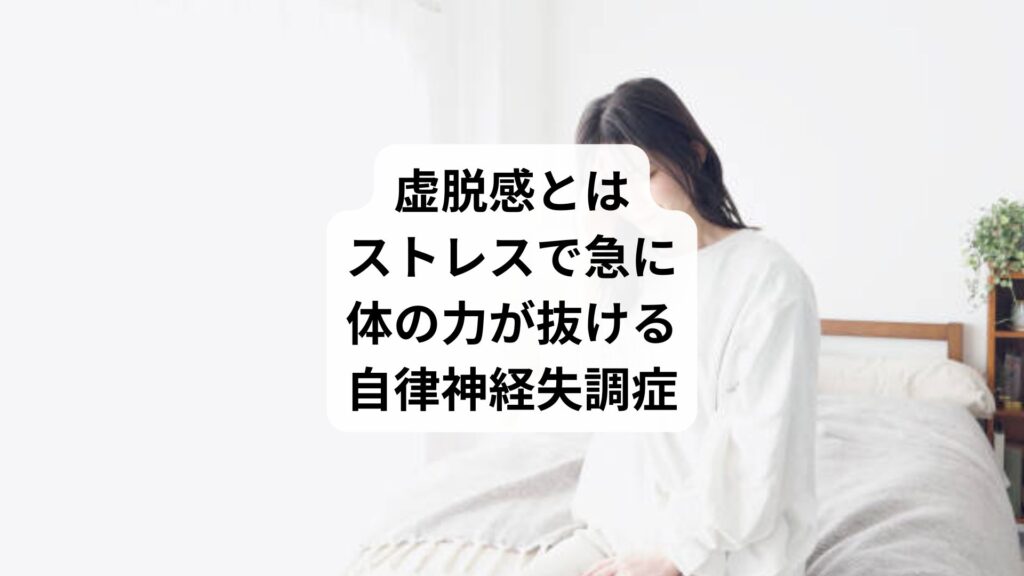
公開日:2025年05月06日
更新日:2025年10月16日
このブログを監修している鈴木貴之は国家資格であるはり師免許、きゅう師免許、柔道整復師免許、心理カウンセラーを取得した資格保有者です。
目次
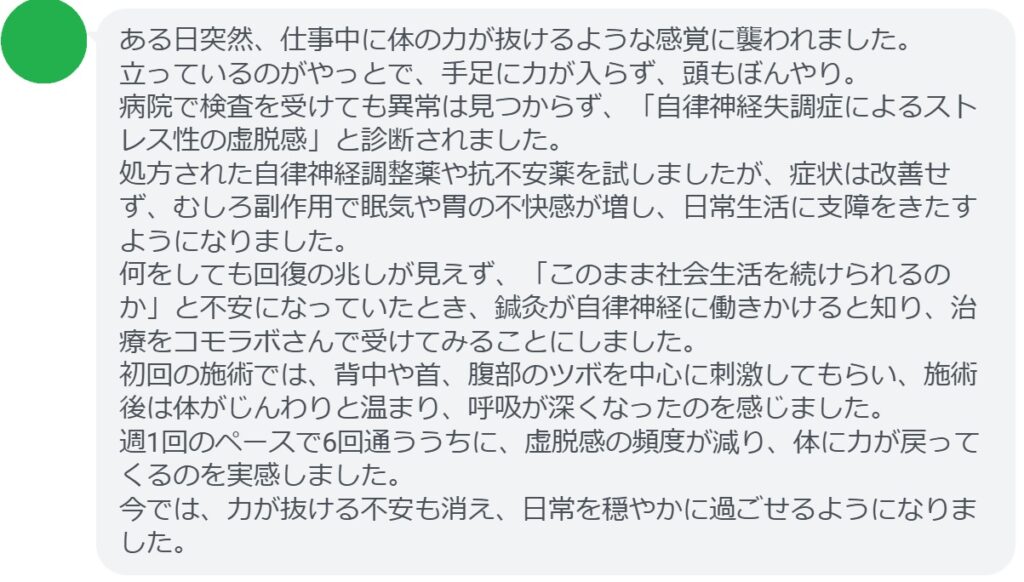
原因不明の脱力感にはストレスが関係
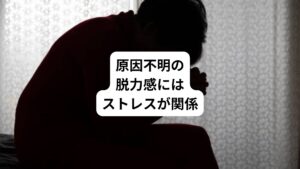
・身体に力が入らず起き上がれない
・脱力感に襲われてやる気が起こらない
・一日中体が重くて動かない
原因不明の脱力感が続くと、何か大きな病気ではないかと不安を感じます。
この脱力感にはストレスが関係している可能性があります。
今回は「虚脱感とは|ストレスで急に体の力が抜ける自律神経失調症」と題して脱力感の原因と対策、関連する疾患について解説します。
体に力が入らない脱力感について

脱力感とは体に力が入らなかったり力が抜けたような状態をさします。
脱力感があると、やる気が起こらないなど行動にも影響が起こります。
仕事のパフォーマンスの低下や家事、食事など普段の生活もできなくなるなどの支障があります。
脱力感を感じる場面は人によってさまざまですが、主に以下のような症状があります。
・朝の寝起きに力が入らず起きられない
・体が重いと感じる
・体に力が入らずやる気が起きない
・体が思うように動かず物を落としやすい
脱力感が起こる原因と対策

脱力感によって何もできない日々を過ごしていると「自分は怠けているだけではないか」と自分を責めてしまうことがあります。
脱力感は気力の問題だけではありません。
実は重大な病気が隠れていることもあります。
そのためまずは脱力感が起こる原因はどこにあるのかを理解することが重要です。
以下の4つの主な原因をご紹介します。
・脳神経伝達の異常
・疲労による血流の低下
・ストレスによる自律神経の乱れ
・栄養不足とくにカリウム不足
脳神経伝達の異常
脱力感の原因のひとつに脳神経伝達の異常が考えられます。
人の体は脳から発生した信号が神経を通って筋肉を動かします。
この脳神経伝達の経路で何らかの障害があると、筋肉に十分に信号が伝わらず体に力が入らなくなります。
瞬間的な脱力感や、手足のしびれを伴う場合は、脳梗塞や脳卒中、てんかんなど脳の疾患の可能性があります。
この場合は内科や脳神経外科など早めに専門医を受診しましょう。
疲労による血流の低下
血流の低下も脱力感の原因のひとつです。
血流の低下により筋肉の血流が不足すると正常に筋肉が収縮せず思うように体を動かすことができなくなります。
血流の低下は睡眠不足や疲労で起こりやすい傾向にあります。
脱力感を感じた時は十分な休息や睡眠をとり体の疲れを解消させましょう。
また運動不足も血行不良の原因となります。
日ごろから運動不足を感じる人は、適度な運動で筋肉を動かし血液の循環を良くすることも重要です。
ストレスによる自律神経の乱れ
脱力感はストレスなどによる自律神経の乱れによっても出現します。
自律神経は主に全身の器官の働きを調節する神経です。
この自律神経はストレスの影響を受けやすく、ストレスによって交感神経が活発になります。
交感神経が興奮すると血流の低下を引き起こし脱力感が生じます。
自律神経の乱れはストレス以外にも生活習慣の乱れでも起こります。
生活習慣の修正とともに自分に合ったストレス解消法やリラック方法でストレスを溜め込まないことが大切です。
栄養不足とくにカリウム不足
筋肉を動かすための栄養が不足すると、脱力感を感じる原因となります。
忙しくて食事が十分に摂れていなかったり、偏食で栄養が偏っている人は食生活から見直してみると良いでしょう。
また、栄養の中でもとくにカリウムが不足すると脱力感の症状があらわれやすくなります。
野菜や果物をあまり食べない人は注意が必要です。
ストレスによる脱力感は心の疾患でも起こる

ストレスなどで精神的な疲労が溜まると、意欲の低下とともに脱力感の症状があらわれやすくなります。
「何もする気が起きない」と気分の落ち込みが続くようであれば、以下のような心の疾患の可能性が考えられるため注意が必要です。
・自律神経失調症
・うつ病
自律神経失調症
自律神経失調症は、ストレスや生活習慣の乱れによって自律神経が乱れ、体や心にさまざまな不調が出現する疾患です。
症状は以下の通りです。
・脱力感
・倦怠感
・慢性的な疲労
・頭痛
・不安感
・焦り
・意欲の低下
他の精神疾患の症状と似ていますが、検査によって考えられる病気が除外された時に診断されます。
うつ病
うつ病は、強い気分が落ち込みや意欲の低下などの症状で日常生活に支障が出る病気です。
症状は自律神経失調症とよく似ています。
初期症状では判断することが難しいとされていますが、早期に発見し適切に対処することが大切です。
一般的に以下のような症状が起こります。
・気分の落ち込み
・抑うつ
・意欲の低下
・不眠
・食欲不振
・疲れやすい
症状がほとんど毎日、2週間以上続いた場合はうつ病の可能性があるとされています。
脱力感に対する西洋医学的な治療法について
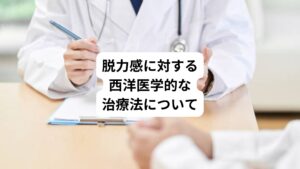
脱力感がうつ病や自律神経失調症など、精神的な疾患による症状と診断されると、薬物療法と併せて心理療法の治療を行います。
患者の症状や程度にあわせて以下のような治療法が選択されます。
・認知行動療法
・対人関係療法
・マインドフルネス
認知行動療法
認知行動療法は、認知の歪みを修正する治療法です。
うつ病の場合は何事においても悲観的に考えてしまう特徴があります。
とくに自分を責めたり落ち込んだりを繰り返して悪循環を生み出す傾向が強いです。
この悪循環を断ち切るために、認知行動療法で柔軟な考え方や問題解決力などを習得します。
物事の考え方や行動が変わると、何か問題や困りごとが起きた時に「自分の力で乗り越えていける」という自己肯定感を養うことができます。
対人関係療法
対人関係療法は、人間関係に存在する4つのテーマのうち、どの領域に問題があるかを明確にして人間関係の改善を目指します。
自分にとって重要な他者と、どのような対人関係にあり、どのような感情があるのかを分析しながら対策法を考え実践していきます。
マインドフルネス
マインドフルネスは、過去の失敗や未来の不安に向いてしまう意識を「今」の感覚に戻し、評価や判断をしない安定した心理状態を保つことに役立ちます。
自分が感じる「今」の感覚と丁寧に向き合うことで、ストレスとうまく付き合う力を養います。
脱力感による不調でお悩みの方はご相談ください
脱力感などのメンタル不調は放置するとうつ病や不眠症など精神疾患に進展してしまう可能性があります。
そのため少しでも不調を感じたらすぐに心身のケアが大切です。
東洋医学では昔からこのような病気になる前のメンタル不調を「未病(みびょう)」と呼び、この未病を治療することを「未病治(みびょうち)」と呼んで治療をする対象にしていました。
「病気になる前から予防のためにメンタルヘルスをケアする」という考えは東洋医学ならではの考えです。
ぜひ、心の不調を感じている方は東洋医学を取り入れてみてはいかがでしょうか。
ストレスによる虚脱感【45歳女性 会社員(東京都在住)】
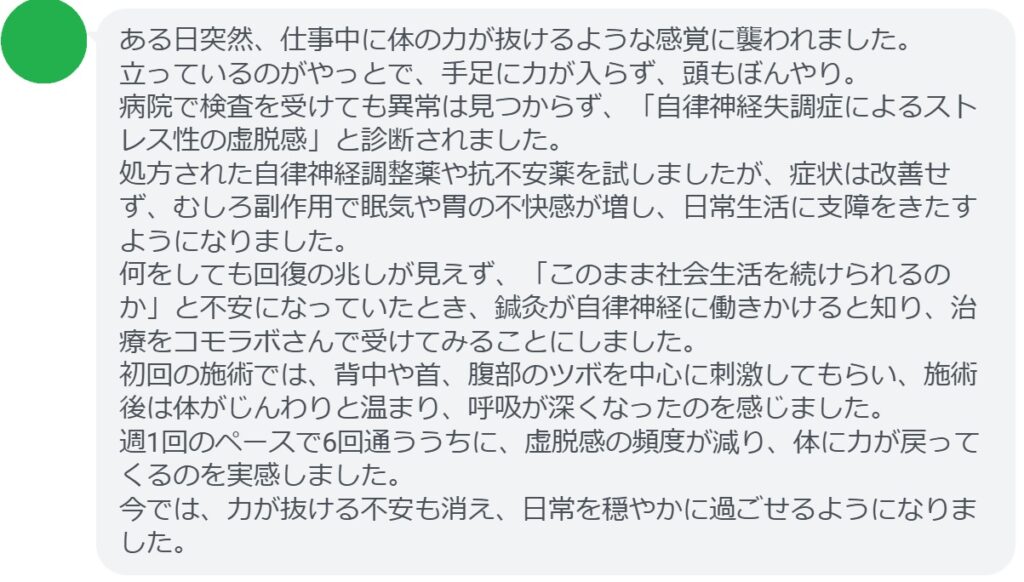
【ストレスによる虚脱感が改善された方の感想(口コミレビュー)】
・東京都在住/45歳女性
ある日突然、仕事中に体の力が抜けるような感覚に襲われました。
立っているのがやっとで、手足に力が入らず、頭もぼんやり。病院で検査を受けても異常は見つからず、「自律神経失調症によるストレス性の虚脱感」と診断されました。
処方された自律神経調整薬や抗不安薬を試しましたが、症状は改善せず、むしろ副作用で眠気や胃の不快感が増し、日常生活に支障をきたすようになりました。
何をしても回復の兆しが見えず、「このまま社会生活を続けられるのか」と不安になっていたとき、鍼灸が自律神経に働きかけると知り、治療をコモラボさんで受けてみることにしました。
初回の施術では、背中や首、腹部のツボを中心に刺激してもらい、施術後は体がじんわりと温まり、呼吸が深くなったのを感じました。
週1回のペースで6回通ううちに、虚脱感の頻度が減り、体に力が戻ってくるのを実感しました。
今では、力が抜ける不安も消え、日常を穏やかに過ごせるようになりました。
実際に当院ご来院になって改善された患者様の声と改善までの経過を報告します。
下記のリンクから別ページでご覧ください。


鍼灸院コモラボ院長
ブログ管理・編集者
鈴木貴之(すずきたかゆき)
【国家資格・所属】
鍼灸あんまマッサージ指圧師、柔道整復師、心理カウンセラー、メンタルトレーナー 治療家歴14年、日本東方医学会会員、脈診臨床研究会会員
神奈川県の鍼灸整骨院にて15年勤務(院長職を務める)
【施術経過の同意について】
本ブログに掲載する施術の経過の情報は「私は本施術の経過を匿名化して貴院のウェブサイトに掲載することに同意します。」と患者様から同意書を得ております。また氏名・連絡先は公開されません。
【医療受診の案内と施術の注意点】
次の症状がある場合は速やかに医療機関を受診してください。強い胸痛、意識障害、急激な症状の悪化、高熱、持続する出血。鍼灸・整体は有益ですが、抗凝固薬服用中、出血傾向、妊娠初期、感染症の疑いがある方は施術前に必ず医師へ相談してください。
現在、JR三鷹駅北口に自律神経専門の鍼灸院コモラボにて様々な不調の患者様に鍼灸治療を行っている。
【SNS】
Youtube , Instagram , X(Twitter)







この症状に対する質問