
BLOG
ブログ
歯列矯正で体調不良|歯列矯正のあと耳管開放症で耳が痛い
- カテゴリ:
- 頭や顔の悩み
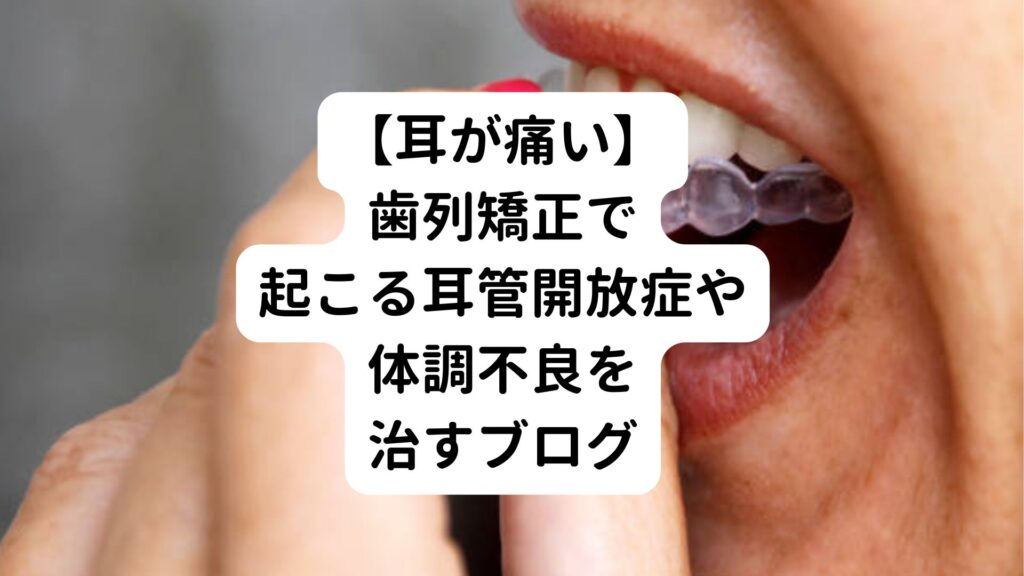
公開日:2024年08月08日
更新日:2024年12月17日
このブログを監修している鈴木貴之は国家資格であるはり師免許、きゅう師免許、柔道整復師免許、心理カウンセラーを取得した資格保有者です。
目次
- 1 歯列矯正で起こる耳管開放症でお悩みの方に適切なアドバイス
- 2 耳管開放症は歯並びの悪さでも起こる
- 3 【耳管開放症の原因①】 過度のストレス
- 4 【耳管開放症の原因②】ホルモンバランス
- 5 【耳管開放症の原因③】生活習慣の乱れ
- 6 耳管開放症に付随して起こる主な症状
- 7 【耳管開放症になる原因①】噛み合わせのバランスが悪い
- 8 【耳管開放症になる原因②】歯科矯正治療中
- 9 【改善するためのポイント①】噛み合わせを修正する
- 10 【改善するためのポイント②】口呼吸を予防する
- 11 【耳管開放症の悪化を防ぐ①】噛み合わせが悪くなる悪習癖を改善する
- 12 【耳管開放症の悪化を防ぐ②】リラックスできる時間を確保する
- 13 歯並びの悪さや歯列矯正による耳管開放症は鍼灸で改善できる
- 14 当院で患者様の治療実績はこちらから
- 15 関連する記事

歯列矯正で起こる耳管開放症でお悩みの方に適切なアドバイス
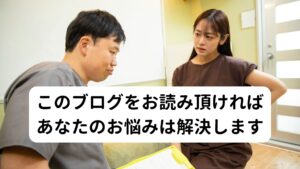
歯並びや歯科矯正は口のだけではなく、全身のバランスにも関係してきます。
とくに全身のバランスが乱れると、耳管開放症と関連してくる可能性が高まります。
自律神経失調症は、さまざまな症状があり、原因を特定することが難しく、できるだけストレスを軽減してリラックスすることが対処療法として求められています。
今回は「歯列矯正で体調不良|歯列矯正のあと耳管開放症で耳が痛い」と題して、歯並びや歯列矯正と耳管開放症の関連について解説します。
耳管開放症は歯並びの悪さでも起こる
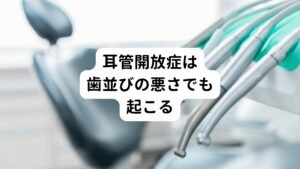
耳管開放症は、交換神経と副交感神経のバランスが崩れることで心身に不調をきたす状態のことをいいます。
耳管開放症は、過度のストレスやホルモンバランスが崩れてしまうことが原因で起きたり、生活習慣が大幅に変わることも引き起こされます。
歯科領域では歯並びが悪いことで噛み合わせのバランスが崩れることがきっかけでも起こります。
とくに嚙み合わせが悪いことで肩こりや頭痛などさまざまな不調を引きおこし、その結果耳管開放症を発症することがあります。
【耳管開放症の原因①】 過度のストレス
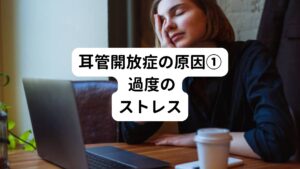
強いストレスは、交感神経が活発に働くため耳管開放症のリスクが高めます。
ストレスの感じ方には個人差があり、まじめな方や几帳面な方はストレスへの耐性が弱い傾向であり耳管開放症のリスクも高くなると考えられています。
ストレスは、環境によるもの、対人関係、ホルモンバランスだけでなく噛み合わせなどによっても生み出されます。
まずは耳管開放症に影響を与えている直接的な原因に対してどのような改善方法ができるか検討し原因を解消していくことが大切です。
ホルモンバランスや噛み合わせであれば治療をすることで改善できるものがあります。
まずは専門医へ相談してみましょう。
また、現代社会ではストレスが完全にない生活は、なかなか難しいでしょう。
適度な運動や読書、ゆったり湯船につかるなど自分に合ったストレスを解消できる方法を見つけて定期的にストレスを解消していくことも重要です。
【耳管開放症の原因②】ホルモンバランス
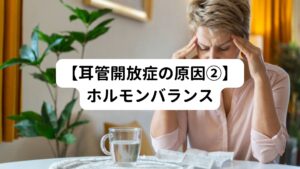
女性はホルモンのバランスが生理周期によって大きく変わる機能をもっています。
特に更年期の時期に色々な症状が出現し、ほてり、イライラ、不安感などの症状が出ることがあります。
この反応は女性ホルモンを出す部分と自律神経の位置が近い場所に位置していることも関係しており、影響し合っているために起こります。
女性ホルモンは更年期を境に減少傾向になり耳管開放症を患いやすいやすくなりますが、思春期の増加する時期でも同様に変化が起きるため、この時期でも耳管開放症になりやすいと考えられています。
また、ホルモンの減少は女性だけでなく男性でも起こります。
そのため、男性でも更年期の時期には耳管開放症にかかる可能性があります。
【耳管開放症の原因③】生活習慣の乱れ
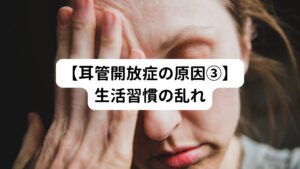
自律神経は交感神経と副交感神経に分かれています。
交感神経は身体が活発に動く時に働き、反対に副交感神経は身体を休める時に働きます。
耳管開放症になると、この切り替えがうまくできません。
この耳管開放症は生活習慣が乱れていることでも起こります。
そのため改善と予防には規則正しい生活習慣を身につけることが重要です。
生活習慣は、主に「睡眠時間」「食生活」「起床時間」を整えることが重要でさらにそれをルーティン化する必要があります。
例えば朝はきちんと起きて、太陽を浴びる生活などが大切です。
夜型の生活になっている方は、その生活自体がストレスやホルモンバランスが乱れる原因になることがあるので改善しましょう。
耳管開放症に付随して起こる主な症状
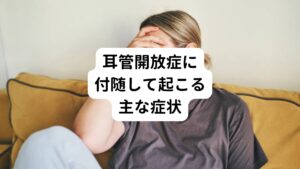
【身体的症状】
・だるさ
・めまい
・耳鳴り
・頭痛
・肩こり
・動悸
・息切れ
・ほてり
・汗が多い
【精神的症状】
・落ち込み
・うつ症状
・イライラ
・不安感
・焦り
・やる気が出ない
これらの症状が出ると、「朝起きられない」「家事ができない」などの症状で日常生活に支障が出て、引きこもりがちになったり、外出しなくなったりします。
耳管開放症は症状があっても、内科などでは原因が分からず治療方法もないため、さらにストレスを感じる場合もあります。
【耳管開放症になる原因①】噛み合わせのバランスが悪い
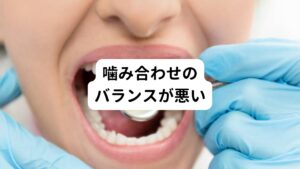
噛み合わせが悪いまま食事を続けていると、上の歯と下の歯が強く当たっている部分に負担がかかったり、顎関節に必要以上に負担がかかったりすることがあります。
この状態は口周りの筋緊張だけでなく、肩や首などまで緊張して首こりや肩こりの症状が起こります。
この状態を放置すると首こりや肩こりから頭痛などの症状を引き起こすことがあります。
これらの嚙み合わせによる関連痛が心身のストレスとなって耳管開放症を引き起こす可能性があります。
【耳管開放症になる原因②】歯科矯正治療中

歯並びや噛み合わせのバランスを整える矯正治療ですが、治療の過程で歯が動くために噛み合わせのバランスが変わることがあります。
矯正が完了するまでの一時的な症状ですが、歯が動いて噛み合わせが変わることで耳管開放症が起こることがあります。
【改善するためのポイント①】噛み合わせを修正する

噛み合わせのバランスは食事をする際に重要です。
きちんと噛めることは顎の負担を軽減させてストレスが溜まることがありません。
また、正しく噛み合わせていると、スポーツの際のパフォーマンスにもよいといわれています。
一流のアスリートは瞬間的な力を出すために、正しい噛み合わせができているのといないのでは結果に差が出ると考えられています。
【改善するためのポイント②】口呼吸を予防する
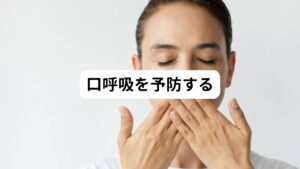
通常は呼吸する際、鼻呼吸が正しい呼吸です。
しかし、歯並びが悪いことで口が閉じにくくなると、口呼吸になってしまいます。
この口呼吸がある方は歯並びが悪い状態である可能性があります。
そのため、矯正治療をすると、口が閉じやすくなり、口呼吸が改善しやすくなります。
さらに口を閉じて呼吸をすることが維持できれば、歯並びはバランスを保つことができます。
しかし、口呼吸によって口が開いたままになると歯並びが悪くなってしまいます。
また、口が乾燥しやすくなるので、細菌が増殖しやすくなり虫歯や歯周病のリスクも高めます。
そのほかには、鼻には鼻毛によるフィルター機能でウイルスや細菌からの侵入を守っていますが、口にはその役割がないため、ウイルスや細菌をダイレクトに吸い込んでしまい、感染症のリスクが高めてしまいます。
【耳管開放症の悪化を防ぐ①】噛み合わせが悪くなる悪習癖を改善する
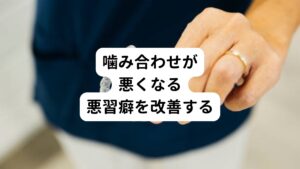
・頬杖をつく
・食事の際に偏った方で食べる
・立った時の重心を片足だけにかける
・爪をかむ
・舌で歯を押す
これらは、噛み合わせや歯並びが悪くなる悪習癖です。
せっかく矯正治療をして、歯並びを整えてもこれらをしてしまうと後戻りをする原因です。
こういった癖によって噛み合わせが悪くなると、耳管開放症の可能性が出てきますので、すぐに改善するようにしましょう。
【耳管開放症の悪化を防ぐ②】リラックスできる時間を確保する

耳管開放症の主な原因である過度なストレスは解消していくことで耳管開放症の症状改善や予防につながります。
そのため忙しい毎日の中でもリラックスできる時間をしっかり確保してストレスを軽減していきましょう。
とくに入浴は自律神経を整えるのに効果が期待できるといわれています。
身体を温めることで、血行もよくなりますし、疲労回復の効果も見込めます。
歯並びの悪さや歯列矯正による耳管開放症は鍼灸で改善できる
歯並びの悪さや嚙み合わせの不具合によって起こる耳管開放症は身心のストレスや顎周囲にある筋肉のアンバランスによって起こります。
また最近では精神的なストレスによって交感神経が過剰に興奮することでも嚙み合わせの不具合が生じて耳管開放症が起こることもあります。
こういった筋肉のアンバランスや自律神経の乱れによる耳管開放症は東洋医学に基づく鍼灸が効果的です。
この東洋医学に基づく鍼灸治療は一人ひとりの体質を診断することで噛み合わせの不具合が起きている原因を各々の体質から発見し改善することができます。
「どこに行けば自分の不調を正しく改善できるかわからない」と治療方法でお悩みの方は当院にお気軽にご相談ください。
当院で患者様の治療実績はこちらから
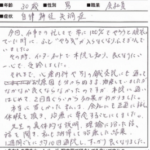
実際に当院ご来院になって改善された患者様の声と改善までの経過を報告します。
同じようにつらい思いをされている方の役に立てるのならばと皆さん快く掲載を許可頂きました。
これを読まれている患者様のご参考になれば嬉しく思います。
下記のリンクから別ページでご覧ください。


鍼灸院コモラボ院長
ブログ管理・編集者
【国家資格・所属】
鍼灸あんまマッサージ指圧師、柔道整復師、心理カウンセラー、メンタルトレーナー 治療家歴14年、日本東方医学会会員、脈診臨床研究会会員
神奈川県の鍼灸整骨院にて13年勤務(院長職を務める)
現在、JR三鷹駅北口に自律神経専門の鍼灸院コモラボにて様々な不調の患者様に鍼灸治療を行っている。
【SNS】
Youtube , Instagram , X(Twitter)







この症状に対する質問