
BLOG
ブログ
抗不安薬は飲まない方がいい理由|抗不安薬をやめるタイミングの知恵袋
- カテゴリ:
- 全身のお悩み
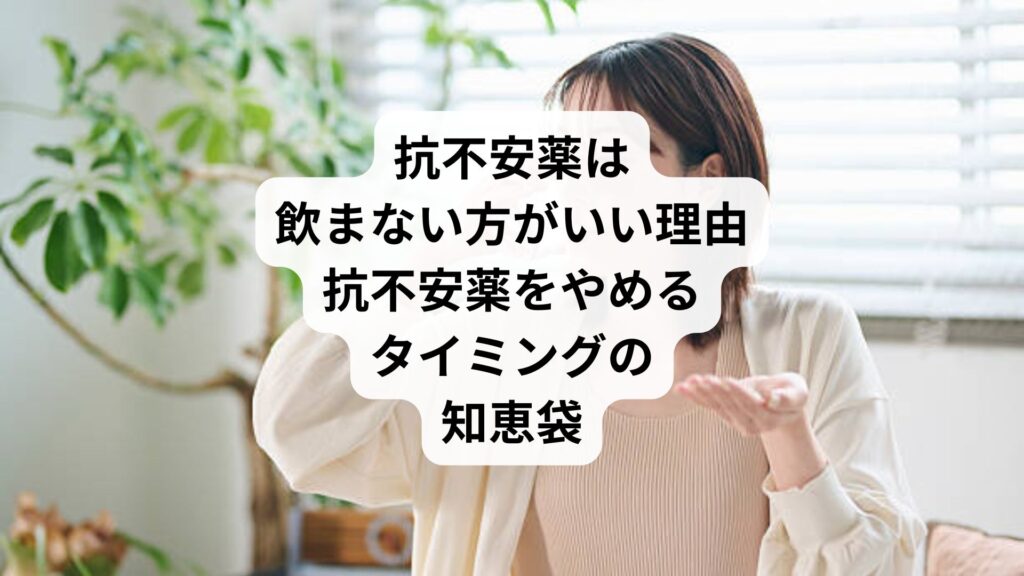
公開日:2024年07月18日
更新日:2025年10月03日
このブログを監修している鈴木貴之は国家資格であるはり師免許、きゅう師免許、柔道整復師免許、心理カウンセラーを取得した資格保有者です。
目次
- 1 抗不安薬の服用で悩まれている方に適切なアドバイス
- 2 抗不安薬は一般的には精神安定剤と呼ばれている
- 3 精神科では患者の主訴に合わせてそのまま薬物が処方される
- 4 抗不安薬には4つの効果がある
- 5 生活環境に合わせて抗不安薬の作用を選んでいる
- 6 4つの作用と薬の強さは必ずしも連動しているわけではない
- 7 減薬や断薬を考慮して処方している病院は少ない
- 8 医師は減薬や断薬のことまで責任をもって処方をしていない
- 9 不安が起こる根本的な原因は薬物で解消されない
- 10 抗不安薬を減薬しながら不調を治すなら東洋医学の鍼灸治療が効果的
- 11 抗不安薬の減薬と断薬【35歳女性 会社員(神奈川県在住)】
- 12 関連する記事
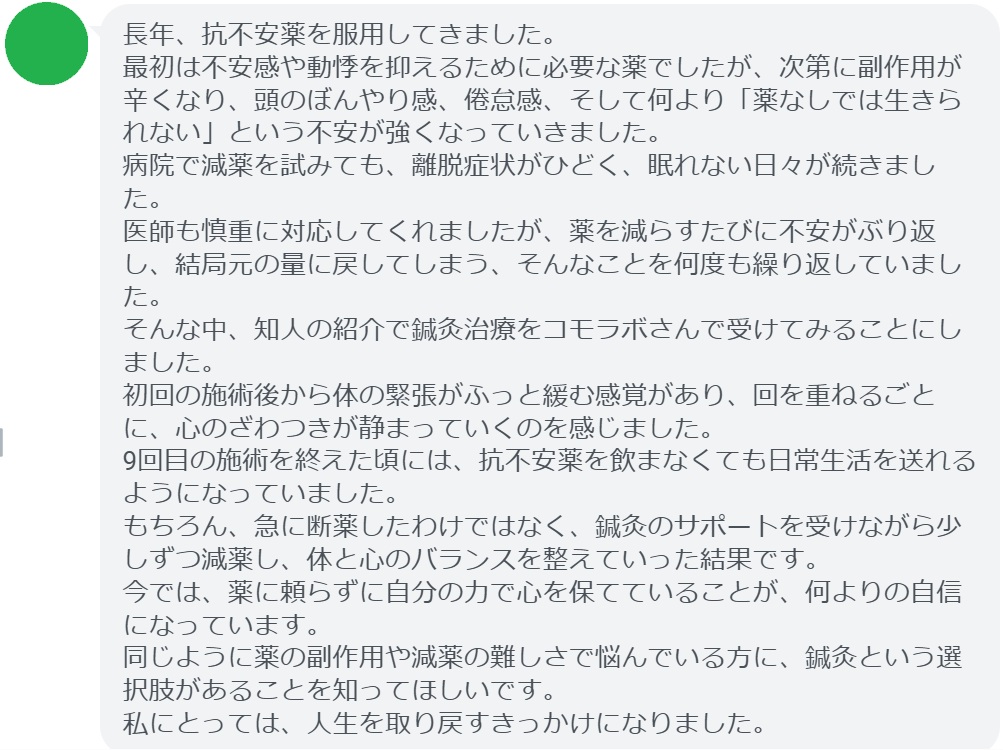
抗不安薬の服用で悩まれている方に適切なアドバイス
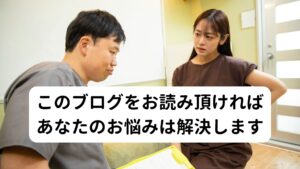
抗不安薬を中長期的に服用し続けている方の多くは、
「最初は効き目を感じたが次第に効かなくなった」
「途中から薬が変更されたり、薬の量が増量された」
という体験をします。
この薬の切り替えや薬の増量で副作用や薬害が起こり深刻な不安感や目の不調(眼瞼けいれん)や耳鳴り、頭痛、イライラなどの身体症状が起こります。
また薬を少し減らしただけで強い睡眠障害や筋肉の硬直や痛みといった状況に悩まされている場合も少なくありません。
今回は「抗不安薬は飲まない方がいい理由|抗不安薬をやめるタイミングの知恵袋」と題して精神科医や心療内科で処方される「抗不安薬」について解説します。
抗不安薬は一般的には精神安定剤と呼ばれている
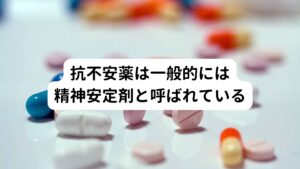
精神科や心療内科に行って不安症状を訴えると主に処方されるのものが「抗不安薬」、一般的には「精神安定剤」と呼ばれる種類の薬物です。
強い不安を感じると心身へのストレスも強くなり、自律神経のバランスも崩れて色々な不調が起きます。
不安によって眠れなくなることも多いため、多くの患者様は不安症状と睡眠障害をともに訴えることも多い傾向にあります。
精神科では患者の主訴に合わせてそのまま薬物が処方される
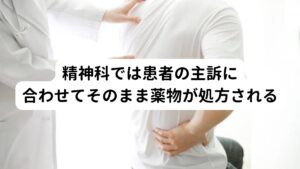
そのため精神科を受診し不眠の訴えが強ければ睡眠薬が処方され、強い不安やパニック的なことを訴えれば抗不安薬の処方ということになり、じつは精神科や心療内科では客観的な検査というものがなく、患者の主訴に合わせてそのまま薬が処方されます。
また最近では整形外科などでも、体の痛みを訴える患者に対してデパスやリボトリールなど筋弛緩作用のあるベンゾジアゼピン系の抗不安薬が処方されており、様々な不調に対して抗不安薬が使われています。
抗不安薬には4つの効果がある
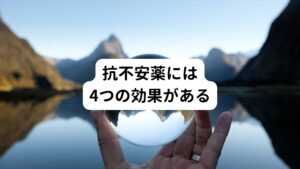
薬の種類という点で見ると、抗不安薬も睡眠薬もベンゾジアゼピン系という種類としては同じ仲間の薬になります。
各薬にはそれぞれ得意分野にがあるとされています。
抗不安薬には、
①不安を抑える抗不安作用
②眠気を誘う催眠作用
③緊張を緩める筋弛緩作用
④けいれんを抑える抗けいれん作用
という4つの効果があります。
生活環境に合わせて抗不安薬の作用を選んでいる
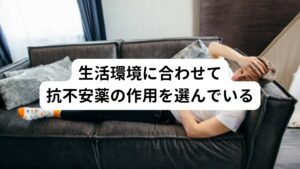
また医師が抗不安薬を処方する時、目安にするのはこの4種類の作用時間です。
この作用時間には、短期型、中間型、長時間型、超長時間型の4種類があります。
医師は、患者の生活環境に合わせた作用時間と欲しい効果などから妥当を思われる抗不安薬を選択します。
主に
・抗不安薬の効果の強さ
・薬の強さであるジアゼパム 換算(数値が少ない方が効果が強い)
・半減期(薬の濃度が血液中で半分になるまでの時間)
などを考慮しています。
※選択の条件をまとめた一覧は上記の画像になります。
4つの作用と薬の強さは必ずしも連動しているわけではない
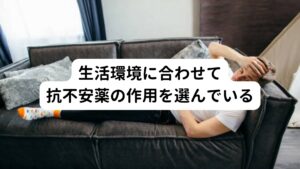
抗不安薬を並べてみると抗不安作用、催眠作用、筋弛緩作用、抗けいれん作用という4つの効果にはそれぞれ得手不得手があります。
医師はこういった情報を元に患者に処方する抗不安薬を選ぶのだと思いますが、必ずしも各効果と薬の強さは連動しない感じもあります。
しかし、このような薬物の特徴や効果の強みなどは、各製薬会社が自社の薬の販売のために発信している情報です。
各薬は承認された時期も異なるため上記の表はその薬剤の持つ相対的な特徴の比較とはいえないかもしれません。
減薬や断薬を考慮して処方している病院は少ない
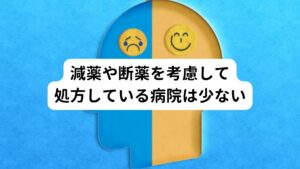
また処方時に選択される薬の強さ、弱さにも色々な観点があり正しい処方であるかを医師自体が判断するのはとても困難です。
ようするに「飲んでみなければわからない」という状態で処方している状態が昨今の精神科や心療内科での処方だと考えられます。
しかも、その状態から薬を減薬したり断薬する時に起こる身体への影響についてはほとんど医学的な情報はありません。
処方する時点では減薬や断薬を念頭に置いている精神科や心療内科は非常に少ないと思います。
医師は減薬や断薬のことまで責任をもって処方をしていない
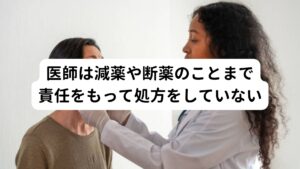
この処方の問題によって起こるのが「抗不安薬・睡眠薬などのベンゾジアゼピン系の薬物で耐性が起きて減薬や断薬のときに不快な離脱症状が出現する」ということです。
こういった危険性がありながら薬をやめる時や減らす時にどのようなことが起こるのかはあまりしっかりとした研究が西洋医学ではされてないのが現状です。
そのため薬を処方する時は、薬の特徴を理解している医師であったとしても「減らす時のことまで責任を持って処方してくれるわけではない」ことを理解した上で減薬や断薬を計画した上で服用を開始するようにしましょう。
不安が起こる根本的な原因は薬物で解消されない
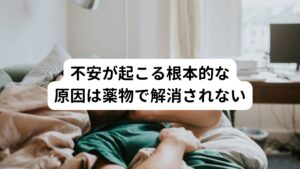
また不安が起こる根本的な原因は薬物で解消されるわけではありません。
抗不安薬によってできることは一時的に脳の感覚を麻痺させるだけということも理解しておくことが重要です。
抗不安薬を期限付きの「対症療法」として利用すると決心したうえで計画的な服薬と減薬について主体的に考えることが必要です。
抗不安薬を減薬しながら不調を治すなら東洋医学の鍼灸治療が効果的
西洋医学では不安症やパニック障害への治療は薬物療法が主流です。
処方される薬には中枢神経に作用する抗不安薬も多く依存性と離脱症状が懸念されます。
完治に至るまでの期間が長ければ長いほど服薬する期間も長くなるため依存する確率も高くなります。
しかし、東洋医学に基づく鍼灸治療は依存性が全く無く不安症やパニック障害の改善が行えます。
また抗不安薬を減薬しながら不安症を治すことも可能です。
ぜひ、当院の鍼灸治療を受けならがら減薬や断薬をしてみてはいかがでしょうか。
抗不安薬の減薬と断薬【35歳女性 会社員(神奈川県在住)】
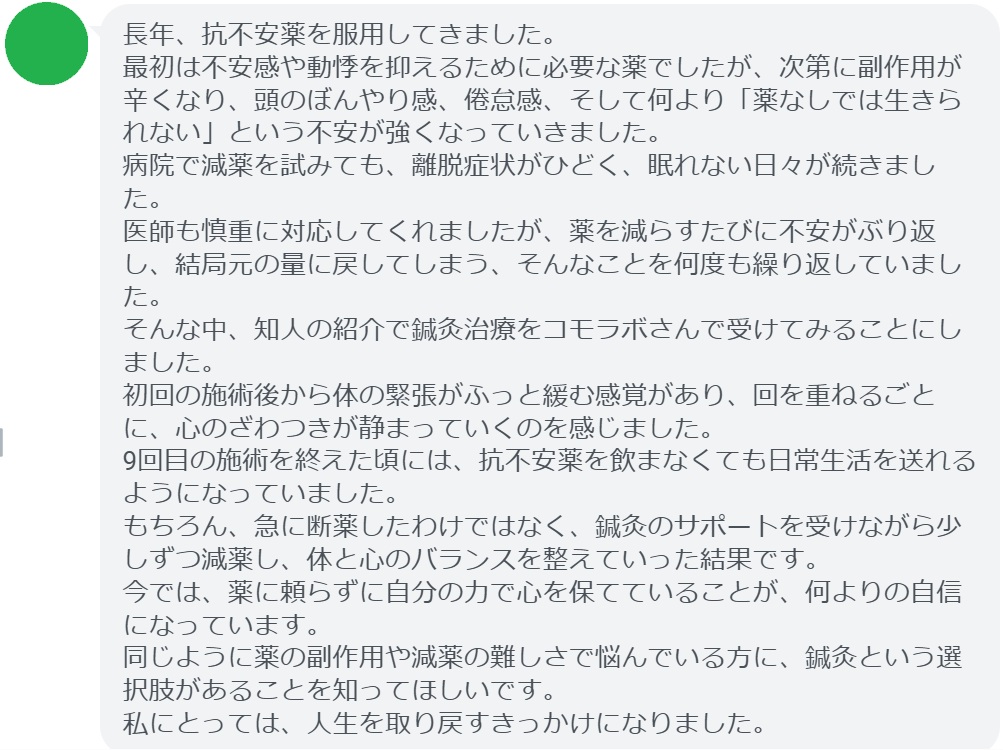
【抗不安薬の減薬と断薬が成功された方の感想(口コミレビュー)】
・神奈川県在住/35歳女性
長年、抗不安薬を服用してきました。
最初は不安感や動悸を抑えるために必要な薬でしたが、次第に副作用が辛くなり、頭のぼんやり感、倦怠感、そして何より「薬なしでは生きられない」という不安が強くなっていきました。
病院で減薬を試みても、離脱症状がひどく、眠れない日々が続きました。
医師も慎重に対応してくれましたが、薬を減らすたびに不安がぶり返し、結局元の量に戻してしまう、そんなことを何度も繰り返していました。
そんな中、知人の紹介で鍼灸治療をコモラボさんで受けてみることにしました。
初回の施術後から体の緊張がふっと緩む感覚があり、回を重ねるごとに、心のざわつきが静まっていくのを感じました。
9回目の施術を終えた頃には、抗不安薬を飲まなくても日常生活を送れるようになっていました。
もちろん、急に断薬したわけではなく、鍼灸のサポートを受けながら少しずつ減薬し、体と心のバランスを整えていった結果です。
今では、薬に頼らずに自分の力で心を保てていることが、何よりの自信になっています。
同じように薬の副作用や減薬の難しさで悩んでいる方に、鍼灸という選択肢があることを知ってほしいです。
私にとっては、人生を取り戻すきっかけになりました。
※他にも実際に当院ご来院になって改善された患者様の声と改善までの経過を報告しています。
下記のリンクから別ページでご覧ください。


鍼灸院コモラボ院長
ブログ管理・編集者
鈴木貴之(すずきたかゆき)
【国家資格・所属】
鍼灸あんまマッサージ指圧師、柔道整復師、心理カウンセラー、メンタルトレーナー 治療家歴14年、日本東方医学会会員、脈診臨床研究会会員
神奈川県の鍼灸整骨院にて15年勤務(院長職を務める)
【施術経過の同意について】
本ブログに掲載する施術の経過の情報は「私は本施術の経過を匿名化して貴院のウェブサイトに掲載することに同意します。」と患者様から同意書を得ております。また氏名・連絡先は公開されません。
【医療受診の案内と施術の注意点】
次の症状がある場合は速やかに医療機関を受診してください。強い胸痛、意識障害、急激な症状の悪化、高熱、持続する出血。鍼灸・整体は有益ですが、抗凝固薬服用中、出血傾向、妊娠初期、感染症の疑いがある方は施術前に必ず医師へ相談してください。
現在、JR三鷹駅北口に自律神経専門の鍼灸院コモラボにて様々な不調の患者様に鍼灸治療を行っている。
【SNS】
Youtube , Instagram , X(Twitter)







この症状に対する質問