
BLOG
ブログ
あくびで顎の下がつる原因と治し方|舌の付け根に原因?
- カテゴリ:
- 頭や顔の悩み
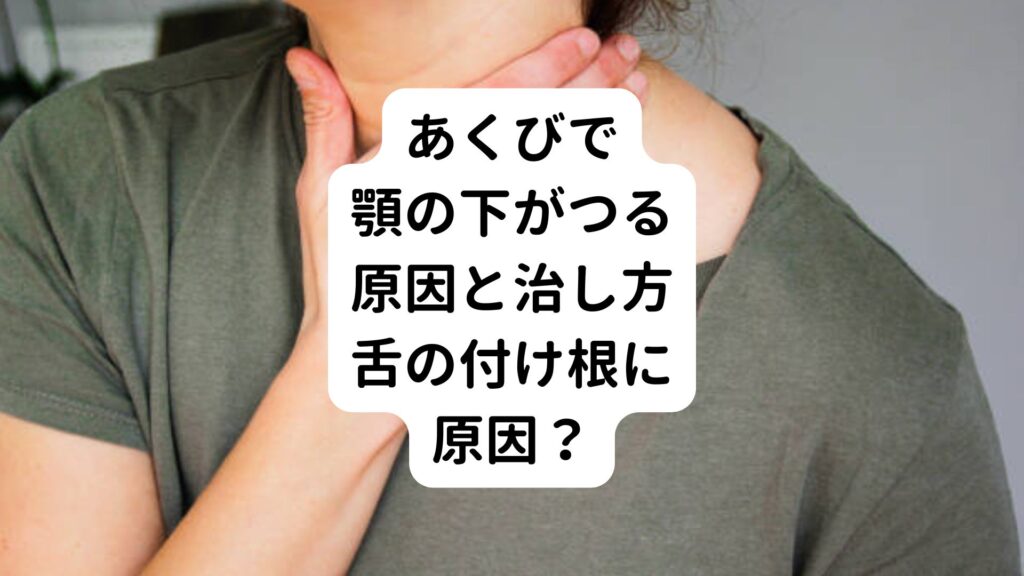
公開日:2024年01月31日
更新日:2025年09月20日
このブログを監修している鈴木貴之は国家資格であるはり師免許、きゅう師免許、柔道整復師免許、心理カウンセラーを取得した資格保有者です。
目次
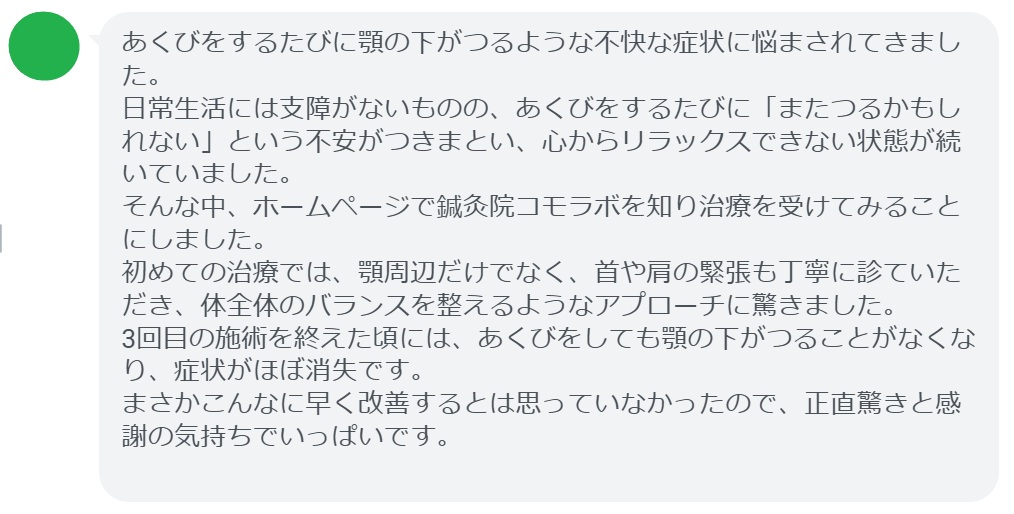
あくびで顎の下がつる症状でお悩みの方に適切なアドバイス
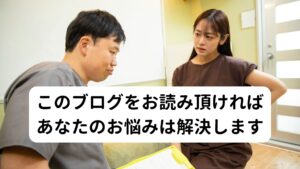
「あくびをすると顎の下がつるような感じがする」
「あくびをすると舌の付け根がつって痛む」
「あくびで首がつるような痛みがでる」
このような症状でお悩みの方はおられないでしょうか。
顎の不調で悩んでいる方に「あくびをすると顎がつる、こむら返りが起こる」という症状でお悩みの方が多くおられます。
このようなあくびにおける顎の不調でお悩みの方の共通点に「急に、顎の下に痛みが出た」「あくびで舌の付け根がつる」「喉がつる感じがある」といった不調を訴える傾向があります。
このような症状が起こる原因には「舌骨上筋群」が関係しています。
今回は「あくびで顎の下がつる原因と治し方|舌の付け根に原因?」と題してあくびで顎がつるメカニズムや原因と改善方法を解説します。
顎がつったり、こむら返りが起こる原因
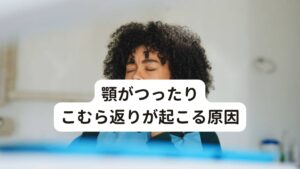
あくびによる顎につる症状が起こるのは噛むために必要な顎の筋肉(咀嚼筋、特に外側翼突筋)に運動障害が起こるためです。
顎の筋肉に無理な力が加わったり、自律神経系のバランスが崩れ、筋肉が緊張状態になると「こむら返り」の様な症状が起こります。
結果として「口を開けたときにつる」「こむら返りが起こる」などの症状が現れます。
この顎のつり症状を放置したままにすると、顎の筋肉の緊張から肩こり、頭痛、めまいなど自律神経失調症による全身症状が出てしまいます。
症状が続くと自律神経系の不調がひどくなり、さらにそのことが「食いしばりや歯ぎしり」などを引き起こします。
症状が悪化するという悪循環が形成され、治らなくなってしまいます。※1
顎の下に痛みが出やすいのはなぜか

よくあくびによる顎のつり感で痛みを感じやすい箇所に「顎の下」があります。
この場所にある筋肉は「舌骨上筋群(ぜっこつじょうきんぐん)」と呼ばれる、舌骨というU字型の骨の上にある小さな筋肉です。
この舌骨上筋群の働きには「物を飲み込む(嚥下)」など喉の動きにかかわっています。
この舌骨は舌骨上筋群で下顎骨や頭蓋骨につながっており、下にある舌骨下筋群で胸骨や肩甲骨へつながっています。
そのため舌骨上筋群の動きが悪くなると連動して舌骨下筋群にも影響を及ぼします。
顎の下の痛みを放置すると肩こりや肩こり頭痛が起こりやすいというのはこういった構造によるものからも起きています。※2
あくびによる顎のこむら返りが起こりやすい人の特徴
![あくびによる顎のこむら返りが起こりやすい人の特徴あくびによる顎のこむら返りが起こりやすい人の特徴は以下の通りです。
[特徴]
・集中すると首や肩に力が入りやすい
・ストレスを感じると眠りが浅くなる
・朝起きると顎が張っている
・頭痛が起きやすい
・咀嚼すると顎が疲れやすい](https://comlabollc.co.jp/blog/wp-content/uploads/2024/01/eq10-2024-01-31T101911.502-300x169.jpg)
あくびによる顎のこむら返りが起こりやすい人の特徴は以下の通りです。
[特徴]
・集中すると首や肩に力が入りやすい
・ストレスを感じると眠りが浅くなる
・朝起きると顎が張っている
・頭痛が起きやすい
・咀嚼すると顎が疲れやすい
顎のつりやこむら返りを予防するための方法
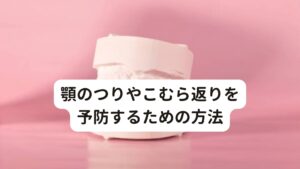
顎や喉の周りにある筋肉(とくに舌骨上筋群)が硬くなってしまうことで、顎の動きが悪くなってしまいます。
この筋肉の硬さをほぐし、下顎を正しい位置に戻すためのストレッチを紹介します。
①歯と歯を合わせて「い」の口の形を作る
②下顎をゆっくり右に動かし、左にも動かす(右から左にゆっくりスライドする)
③口を大きく開けたまま、下あごを右にスライドさせ、ゆっくり口を閉じる
④同じように左で繰り返す 1~4を 右回り、左回り で2回ずつ繰り返します。
当院最新の症例報告と知恵袋

【当院の最新情報】
顎の下がつる原因には「舌骨上筋群」が関係していると解説しました。
しかし、最近の臨床では「胸鎖乳突筋」と呼ぶ筋肉が緊張することで「舌骨上筋群」への負担を高めていることがわかってきました。
この胸鎖乳突筋は猫背など不良姿勢によって緊張するため改善のためには姿勢の修正も必要になります。
長時間のデスクワークなどで作業する方は注意が必要です。
顎のつりやこむら返りは鍼灸治療で完治する
このような顎のつりやこむら返りを改善するためには鍼灸治療が効果的です。
鍼灸治療はマッサージや指圧では届きにくい痛みを起こしている筋肉へのアプローチが可能であるため即効性の高い治療が可能です。
また鍼灸には自律神経の乱れを安定させる反応も起こすためリラックス効果を高め食いしばりや歯ぎしりを抑える効果もあります。
ぜひ、治りにくい顎の不調でお悩みの方はご相談ください。
あくびで顎の下がつる【40歳女性 会社員(長野県在住)】
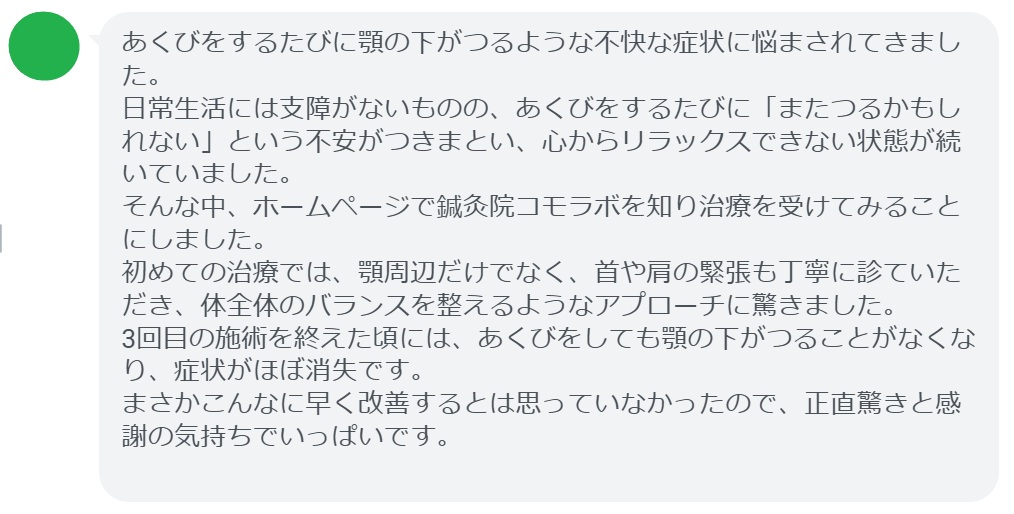
【あくびで顎の下がつる症状が改善された方の感想(口コミレビュー)】
・東京都在住/40歳女性
あくびをするたびに顎の下がつるような不快な症状に悩まされてきました。
日常生活には支障がないものの、あくびをするたびに「またつるかもしれない」という不安がつきまとい、心からリラックスできない状態が続いていました。
そんな中、ホームページで鍼灸院コモラボを知り治療を受けてみることにしました。
初めての治療では、顎周辺だけでなく、首や肩の緊張も丁寧に診ていただき、体全体のバランスを整えるようなアプローチに驚きました。
3回目の施術を終えた頃には、あくびをしても顎の下がつることがなくなり、症状がほぼ消失です。
まさかこんなに早く改善するとは思っていなかったので、正直驚きと感謝の気持ちでいっぱいです。
実際に当院ご来院になって改善された患者様の声と改善までの経過を報告します。
下記のリンクから別ページでご覧ください。

[参考]
顎関節症とは?/筒井歯科医院 ※1
あごの下のこむらがえり/三重大学 発生再生医学研究分野 ※2

鍼灸院コモラボ院長
ブログ管理・編集者
鈴木貴之(すずきたかゆき)
【国家資格・所属】
鍼灸あんまマッサージ指圧師、柔道整復師、心理カウンセラー、メンタルトレーナー 治療家歴14年、日本東方医学会会員、脈診臨床研究会会員
神奈川県の鍼灸整骨院にて15年勤務(院長職を務める)
【施術経過の同意について】
本ブログに掲載する施術の経過の情報は「私は本施術の経過を匿名化して貴院のウェブサイトに掲載することに同意します。」と患者様から同意書を得ております。また氏名・連絡先は公開されません。
【医療受診の案内と施術の注意点】
次の症状がある場合は速やかに医療機関を受診してください。強い胸痛、意識障害、急激な症状の悪化、高熱、持続する出血。鍼灸・整体は有益ですが、抗凝固薬服用中、出血傾向、妊娠初期、感染症の疑いがある方は施術前に必ず医師へ相談してください。
現在、JR三鷹駅北口に自律神経専門の鍼灸院コモラボにて様々な不調の患者様に鍼灸治療を行っている。
【SNS】
Youtube , Instagram , X(Twitter)







この症状に対する質問