
BLOG
ブログ
入浴後の吐き気|お風呂上がりに気持ち悪いときの対処法
- カテゴリ:
- 胸やお腹の悩み
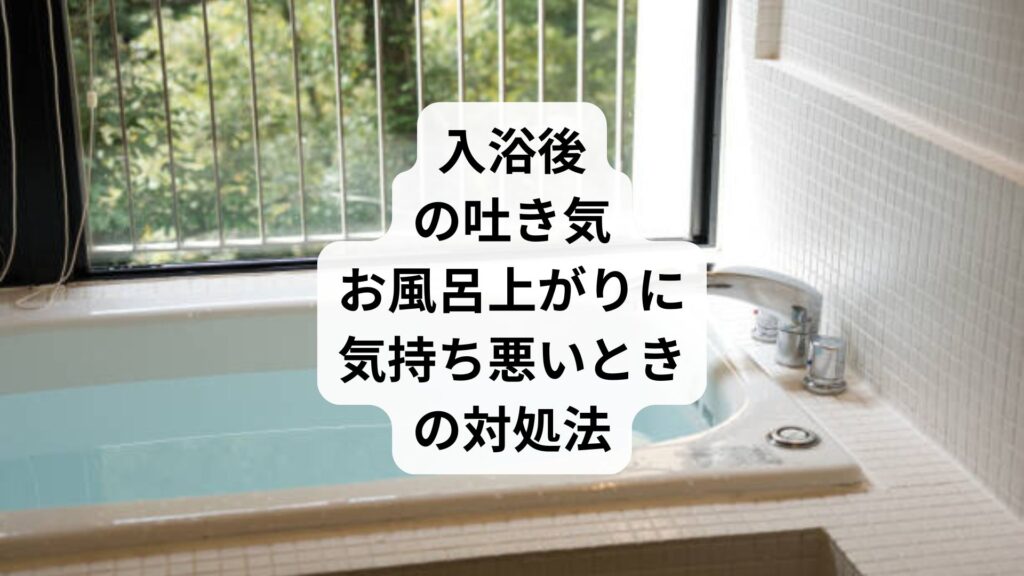
公開日:2022年11月03日
更新日:2025年09月19日
このブログを監修している鈴木貴之は国家資格であるはり師免許、きゅう師免許、柔道整復師免許、心理カウンセラーを取得した資格保有者です。
目次
- 1 お風呂の入浴後に起こる気持ち悪さに要注意
- 2 入浴後の気持ち悪さは血圧の変動が可能性にある
- 3 お風呂上がりのめまいや動悸は東洋医学で対処できる
- 4 【東洋医学①】風呂上りの気持ち悪さの原因は水分代謝の低下
- 5 【東洋医学②】気象病がある人のめまいは水分の停滞が原因
- 6 【東洋医学③】イライラすると動悸が起こる人は気の逆流
- 7 風呂上りの気持ち悪さにおすすめの漢方薬は半夏白朮天麻湯
- 8 【改善例&効果の高いツボ 】高い温度のお風呂に入ると気持ち悪さと動悸がする(30代女性)
- 9 当院最新の症例報告と知恵袋
- 10 入浴後の気持ち悪さの症状は当院の鍼灸で完治と予防ができる
- 11 風呂上がりの気持ち悪さ【45歳女性 会社員(宮城県在住)】
- 12 関連する記事
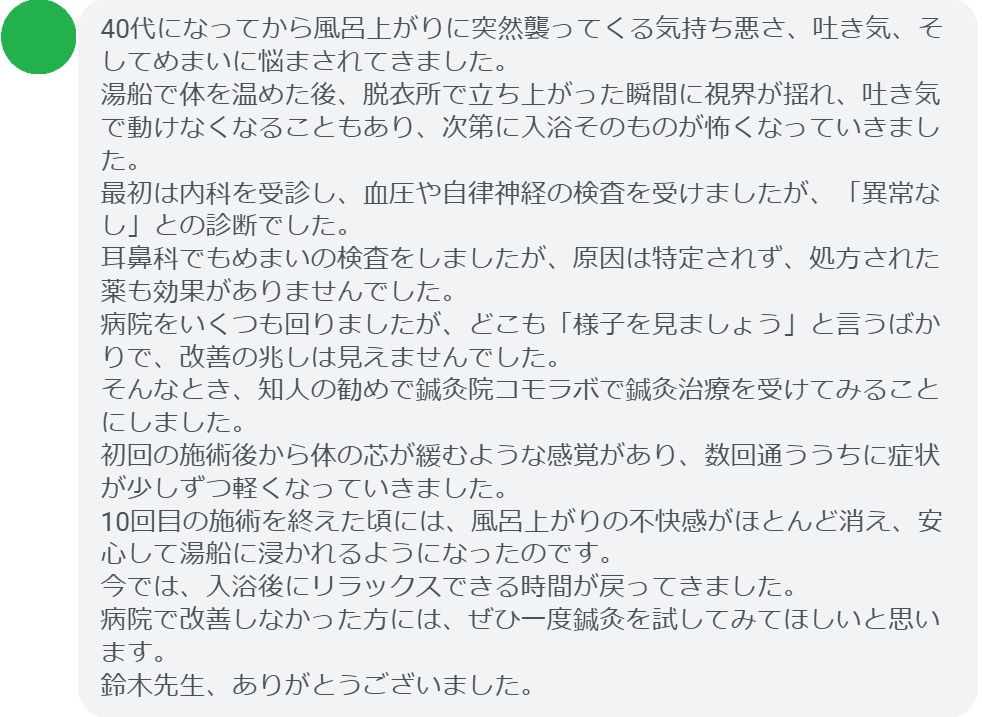
お風呂の入浴後に起こる気持ち悪さに要注意
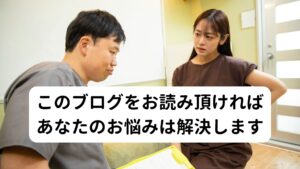
「お風呂上がに気持ち悪さや吐き気がする」
「お風呂上がりに胃もたれのような気持ち悪さがある」
「お風呂上がりにめまいがしてしんどい」
「シャワーの後でも気持ち悪くなる」
このような症状でお悩みの方はおられないでしょうか。
このお風呂上りという状態は身体的には血流、血圧、水分代謝など多くの自律神経の調整が行われるタイミングでもあります。
そのためこの調整に不具合が生じると自律神経症状が起こると考えられており注意が必要です。
今回は「入浴後の吐き気|お風呂上がりに気持ち悪いときの対処法」と題して実際に風呂上りとはどのような状態であるのかを東洋医学の考えで分かりやすく解説します。※1
入浴後の気持ち悪さは血圧の変動が可能性にある
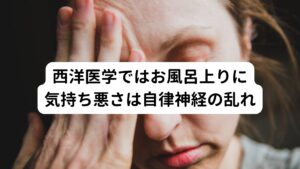
お風呂上りに気持ち悪さや動悸といった不調は頻繁に起こることがあります。
その原因には自律神経が調節している体温調節にあります。
入浴によって体温が上がると身体の熱を放熱させるために体温調節を担う自律神経が働きます。
しかし自律神経が正常に機能しないとコントロールするべき血管や心拍に不具合が生じている可能性があります。
この血管や心拍に不具合が生じると動悸やめまいの症状が起こりやすくなります。
よくあるパターンは入浴中の湯船にしゃがんでいる姿勢から立ち上がるときがあります。
しゃがんでいる姿勢から立ち上がると一気に血圧が下がり起立性調節障害と同じようなめまいが生じるケースがあります。
またひどい人がだとめまいと同時に動悸を起こすこともあります。
これらは西洋医学で解説するとすべて自律神経を介した血液やリンパ液の循環の不具合によって起こると考えられます。※2
お風呂上がりのめまいや動悸は東洋医学で対処できる
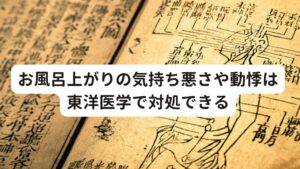
めまいにはふわふわするめまいや立ちくらみから、グルグルと目が回る回転性のめまいまであります。
西洋医学ではこの原因を自律神経を介した耳や脳の異常とされています。
とくに女性では耳の下のリンパが水ぶくれを起こしてめまいが生じるメニエール病という病気にかかる人が多い傾向にあります。
一方、東洋医学では頭部の気(き)・血(けつ)・水(すい)が適切に巡っていないとめまいが起こると考えます。
この気・血・水は東洋医学では人間の組織の3大構成要素として身体にとって重要な物質であり、健康的な身体を作るうえで欠かせないものになります。
自律神経に関わるこのような症状は東洋医学に基づく考え方のほうが体質を細かく分類し治療ができるため効果が高いと考えております。
そのため今回は東洋医学による体質分類で解説します。
【東洋医学①】風呂上りの気持ち悪さの原因は水分代謝の低下
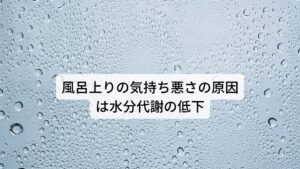
東洋医学では気持ち悪さの症状は胃腸の不調が挙げられます。
胃腸が弱くなると、消化吸収する力が衰えてしまい気の不足(エネルギー不足)になってしまいます。
この気の不足が身体に水分を巡らせる機能を低下させ、頭部に必要な水を持ち上げるエネルギーが不足してしまいます。
その頭部への水不足が気持ちの悪さや動悸を生じさせます。
ほかにはストレスによって身体の熱が上手く放散できずに頭部で溜まることでも吐き気は起こります(いわゆるのぼせ症状)。
【東洋医学②】気象病がある人のめまいは水分の停滞が原因
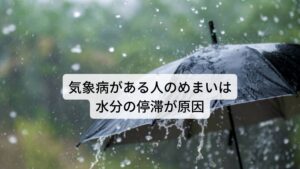
気象病など天気痛がある方がお風呂上りに気持ち悪さやめまいを起こす場合は水分の停滞が原因の可能性があります。
水分の停滞は東洋医学では水滞(すいたい)と呼びます。
水滞は湿気などの影響を受けて水分の巡りが悪くなり頭部に水分が停滞してしまいます。
この水滞を起こしやすいのが気候変動によって不調を起こす気象病です。
この水滞体質の方が風呂上りに起こしやすいのがめまいになります。
また水滞体質の方はめまいだけでなく動悸や吐き気、立ちくらみ症状も起こすことがあります。
【東洋医学③】イライラすると動悸が起こる人は気の逆流
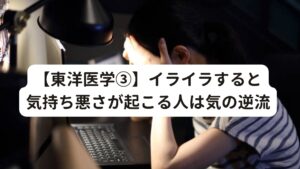
ストレス(イライラや怒りなど)や不安感などが続くと体内で熱が過剰に起こります。
この熱が上昇し頭部に溜まると気が逆流する気逆(きぎゃく)という状態になり身体に不調が起こります。
これがいわゆる「頭に血が上る」という状態です。
この気逆体質が風呂上りに起こる不調は動悸のほか、回転性めまい、頭痛やほてりを伴うこともあります。
風呂上りの気持ち悪さにおすすめの漢方薬は半夏白朮天麻湯

今回解説した東洋医学の分類3つのうち2つ(①と②)は水分に関わる吐き気やめまいです。
この2つに関して効果が期待できる漢方薬は「半夏白朮天麻湯(はんげびゃくぶつてんまとう)」になります。
半夏白朮天麻湯は身体の水分の巡りを改善し水滞を改善させることで吐き気やめまいを治す漢方薬です。
この漢方薬はめまいや吐き気の症状を中心に、頭痛や頭重感、手足の冷えなどの不調を伴うときに用います。
ふだんから胃腸が虚弱で、冷え性や体力がない人に向いている漢方薬です。
【注釈】・・・半夏白朮天麻湯は保険適用もあり、ツムラ37が製品番号になります。服用する場合は医師、薬剤師と相談した上で開始してください。※3
【改善例&効果の高いツボ 】高い温度のお風呂に入ると気持ち悪さと動悸がする(30代女性)

【治療の体験者&改善例 】
30代女性で「数週間前から少し高めの温度のお風呂に入ると動悸が起きたり、気持ち悪くなる」との訴えでご来院されました。
当院に来院される前にクリニックでは「原因不明で自律神経失調症ではないか」との診断を受けていました。
主訴以外の不調をお伺いすると天候の変化などによる頭痛(気象病)、下肢のむくみ、倦怠感、生理痛などがありました。
東洋医学の観点ではこのような不調は「水滞(すいたい)」と呼ばれる体の水分の循環が滞ることで起こるものと考えられます。
そのため鍼灸治療ではツボを上手く利用し体の水分代謝や血流を改善することを目的として行い改善を促しました。
【主に利用したツボ】
尺沢は体の水分の循環を促して呼吸を楽にする働きがあります。気持ち悪さや動悸もスッキリ完治させます。
•尺沢(しゃくたく)・・・肘を曲げた時にできるシワの外側で押して固くなっているところ
当院最新の症例報告と知恵袋

【最新情報】
このお風呂上がりに起こる気持ち悪さの原因は水分代謝の低下によるものがほとんどです。
当院でも様々な症状の患者様をみましたが8割は「水滞」が原因です。
この水分代謝が原因の吐き気を解消させるためには「下肢の血流を高める」ということが最近わかってきました。
そのため当院では鍼や灸によって下肢に重点を置いてアプローチします。
自宅では「ふくらはぎのストレッチ」をするとよいでしょう。
下肢に溜まった水分がスムーズに循環し気持ち悪さが解消されます。
入浴後の気持ち悪さの症状は当院の鍼灸で完治と予防ができる
東洋医学は体質を診断し症状を生み出している根本を改善する治療であるため完治と予防を目指すことができます。
今回の解説のように気持ち悪さと動悸の症状でも個々の体質に違いがあります。この細かな違いを調節して治療することができるのが東洋医学です。
そのため当院ではこの東洋医学に基づく鍼灸治療によって改善を図っています。
「どこに行けば自分の不調を正しく改善できるかわからない」と治療方法でお悩みの方は当院にお気軽にご相談ください。
風呂上がりの気持ち悪さ【45歳女性 会社員(宮城県在住)】
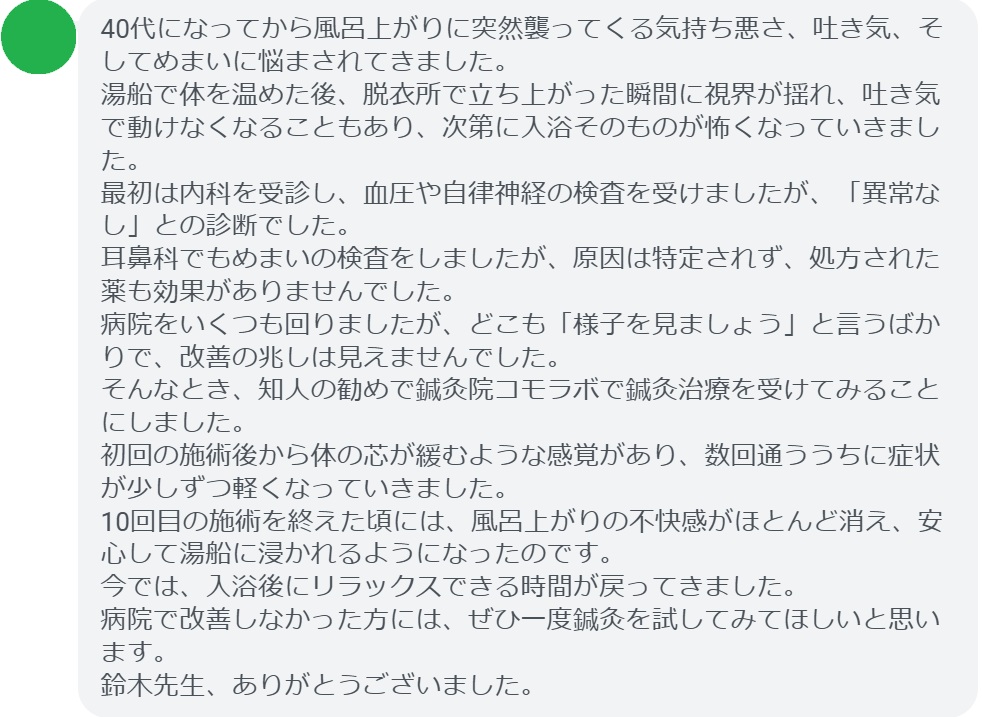
【風呂上がりの気持ち悪さが改善された方の感想(口コミレビュー)】
・東京都在住/45歳女性
40代になってから風呂上がりに突然襲ってくる気持ち悪さ、吐き気、そしてめまいに悩まされてきました。
湯船で体を温めた後、脱衣所で立ち上がった瞬間に視界が揺れ、吐き気で動けなくなることもあり、次第に入浴そのものが怖くなっていきました。最初は内科を受診し、血圧や自律神経の検査を受けましたが、「異常なし」との診断でした。
耳鼻科でもめまいの検査をしましたが、原因は特定されず、処方された薬も効果がありませんでした。
病院をいくつも回りましたが、どこも「様子を見ましょう」と言うばかりで、改善の兆しは見えませんでした。
そんなとき、知人の勧めで鍼灸院コモラボで鍼灸治療を受けてみることにしました。
初回の施術後から体の芯が緩むような感覚があり、数回通ううちに症状が少しずつ軽くなっていきました。
10回目の施術を終えた頃には、風呂上がりの不快感がほとんど消え、安心して湯船に浸かれるようになったのです。
今では、入浴後にリラックスできる時間が戻ってきました。
病院で改善しなかった方には、ぜひ一度鍼灸を試してみてほしいと思います。
鈴木先生、ありがとうございました。
実際に当院ご来院になって改善された患者様の声と改善までの経過を報告します。
下記のリンクから別ページでご覧ください。

[参考]
※1.入浴後の吐き気の原因と対処法|お風呂上がりのしんどさを防ぐ方法を紹介
※2.危険なヒートショック お風呂の事故を防ぐための入浴法/NHK健康チャンネル
https://www.nhk.or.jp/kenko/atc_384.html
※3【漢方処方解説】半夏白朮天麻湯(はんげびゃくじゅつてんまとう)/漢方坂本

鍼灸院コモラボ院長
ブログ管理・編集者
鈴木貴之(すずきたかゆき)
【国家資格・所属】
鍼灸あんまマッサージ指圧師、柔道整復師、心理カウンセラー、メンタルトレーナー 治療家歴14年、日本東方医学会会員、脈診臨床研究会会員
神奈川県の鍼灸整骨院にて15年勤務(院長職を務める)
【施術経過の同意について】
本ブログに掲載する施術の経過の情報は「私は本施術の経過を匿名化して貴院のウェブサイトに掲載することに同意します。」と患者様から同意書を得ております。また氏名・連絡先は公開されません。
【医療受診の案内と施術の注意点】
次の症状がある場合は速やかに医療機関を受診してください。強い胸痛、意識障害、急激な症状の悪化、高熱、持続する出血。鍼灸・整体は有益ですが、抗凝固薬服用中、出血傾向、妊娠初期、感染症の疑いがある方は施術前に必ず医師へ相談してください。
現在、JR三鷹駅北口に自律神経専門の鍼灸院コモラボにて様々な不調の患者様に鍼灸治療を行っている。
【SNS】
Youtube , Instagram , X(Twitter)







この症状に対する質問